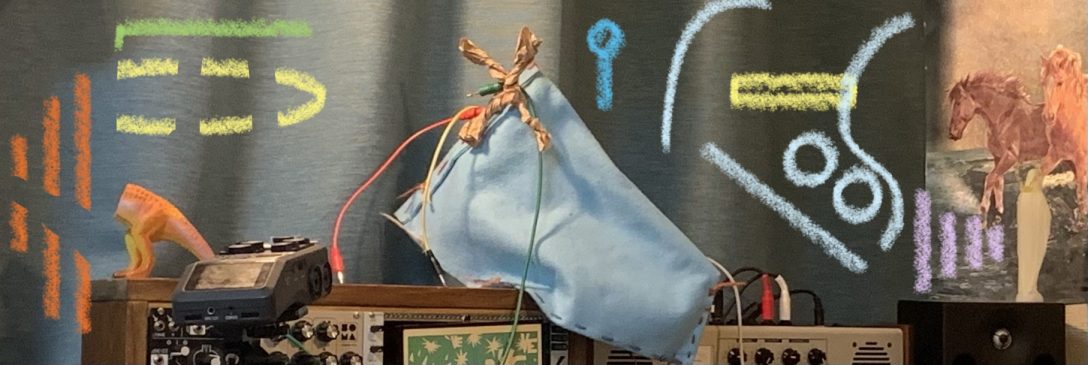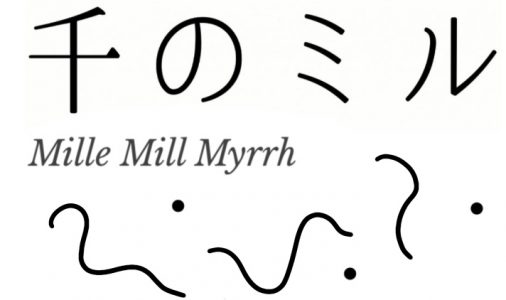ゲームキューブのメインメニューで安ジェネリック系アンビを数分再生し、速度や世界観がどうかしているゲームをプレイ。
一人プレイではできないモードがあってその2人プレイの中の対戦がかなり楽しいゲームなのでSonud testモードにして曲を聴く
City Escape1 第一ステージの曲。メロコア。メロコアって楽しい曲だったんだなあ、と思い出す。ふだん聴かないので。曲の切れ目がわからない編集でループし続けるのでDJ Herveyが魔改造したディスコエディットのようにさっきから延々同じ曲を聴いてる。十回はとっくに!次に行こう。
City Escape2 ゲームキューブのソフトです。爆走。ギターがメタル、アニメタルベビ。
wild canyon ヒップホップ。打ち込みのサックスぽいのがおもちゃの笛のようで良い。ジャック・デラ・ロッチャばりにキレがある。
Green forest 関西出汁とドドンパ娘。
気分を変えてゲームプレイ
チャオガーデン 池のデジタルホワイトノイズ 猫の鳴き声 赤子?redchild 溺れそうな ア・プ・プレ? あうあう
チャオカラテ チャオなるキャラが闘うのだが、やる気がなくなったらB連打がにぎかやし応援してチャオのやる気を出させる。他力というか。他力大事。他力本願て言葉はよくない、自力なんて一人の力、他力は一人以上。
このゲームの島から先は海に入れない、暗い海が不安にさせる見えない壁。
おでかけマシーン メニュー エスニック料理3分番組かわいいチープシンセが
ちからだめし 右から左にパンが振られてもどるタンバリンを模した音 延々聴いてるメニュー画面。
最初の部屋にもどる ハードなテクノ、音量上げる! 手癖で弾いてそうなメロ。