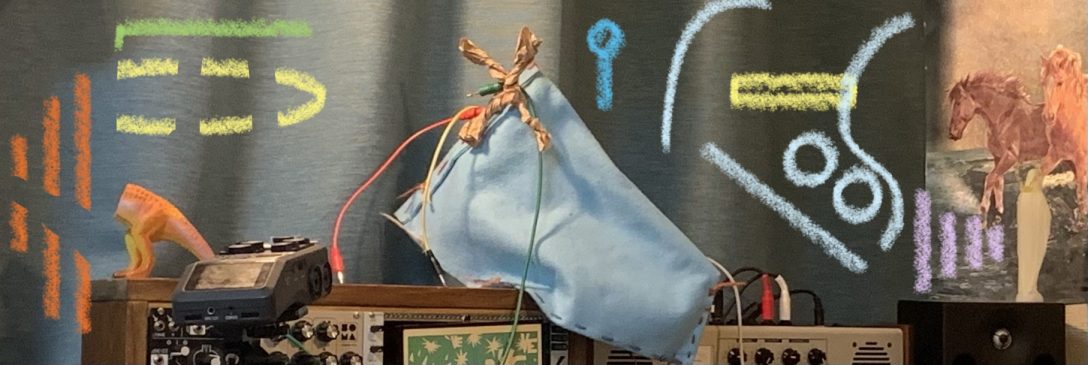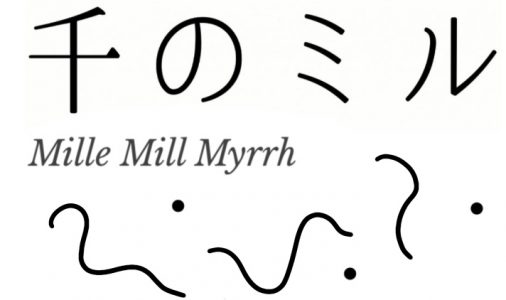Anal solvent
https://youtu.be/atRWLSmsDGg
パリペキンの資料から知った奴ら(個人?)。
恐ろしい名前やね
タグ: 1990s
さよひめぼう / Ninja School, Tomonori Sawada / Transonic Works Plus, Equip / Live in LA
ところでみなさん、さよひめぼうさんの『Ninja School』はもう聴かれましたか? P-VINEからの初CD作品『ALIEN GALAXY MAIL』以来、実に2年振りの新譜は前作のレイヴ面のさらなる拡張解釈というか、『WIPEOUT』を彷彿とさせるレースゲーム的疾走感とエイジアンなミクスチャー感溢れるしたようなハイパーチューンが並んでおり、懐かしくかつ新鮮なもので、本作はあくまでさよひめぼうさん御本人のセルフリリースでして〈New Masterpiece〉からのものでは無いのにもかかわらず知り合いに薦めまくっています。現在本作がらみでちょっとした企画を進行中ですので、来年をお楽しみに。
さて、さよひめぼうさんの新譜と同時期のリリースで自分内シンクロがあった盤がふたつ。Mind Designの片割れ澤田朋伯さんが1990年代〈Transonic〉に残した作品集が来年年始にリリースされます。Mind Designといえば1990年代初期、当時はダサかったはずのフュージョンの要素をうまくデトロイト的に落とし込んでいたテクノユニット(実際デトロイトのレーベルからもEPをリリースしている)という印象でして、かく言う自分がテクノに興味を持つ頃にはその活動期は終わっていたわけですが、その後このフュージョンとデトロイトを折衷する4つうちテクノ路線はKen Ishii『Future In Light』に(おそらく無意識的にでしょうが)継承され、さらに多くのフォロワーを生み出す一方、本人らはゲームミュージックの大家となり『ソニック』をはじめ多くのゲームソフトのサントラを手がけ、現在まで世界中のゲームファンに愛聴されています。ここ数年で驚いたのはVaporwaveの草分け・VektroidのDJ MIXに澤田さんのMind Design時代の代表曲「Skywalk」が収録されていたこと。
で、これも12月発売のEquipの新譜。彼のゲーム好きに関しては私も何度も言及しているし、他所でも多く言及されているので最早お馴染みですが、ここに来て届けられた新譜は自曲のテクノ/トランスアレンジ!!!VGMってこの手のアレンジCDよく出てるし、架空のゲームサントラを題材にする彼にとってこういうパロディに行くのは自明の理なのでしょうが、近しいコンセプトのVAPERROR『Radiant Racer』がクールなエレクトロフュージョンに/FLOOR BABA『PRE HOSTORY』がレイヴ/ベースミュージック方面に締めてるのに対し、ここまでストレートなトランスが出てくるとは彼の今までの作品を聴いていると実に意外でしたね。
最後に収録曲をスクリューした(公式)動画を貼ってこの文章を終わります。スクリューからはじまってスクリューに戻ってくるという、Vaporwaveマナーを忘れないな〜。
高木完/HELLO

先日のDOMMUNEでの配信、私は仕事帰りで飛び飛びでしか見られなかったんですが、前作『ARTMAN』(1997)の話題は上がっていても現時点では本人名義での最終作『HELLO』(1999)はあんまり話題に出てなかった気がしたので、この盤について書こうと思ったんですが、サブスクどころかYouTubeにすら曲が上がっていない始末。確かにHIPHOPからは逸脱し、完全にタガが外れてた時期の作品だからなあ。
『HELLO』収録曲で唯一YouTubeに上がっていたのは、YOU THE ROCK☆をフィーチャーした手塚治虫トリビュート曲。『マグマ大使』(1966)は初代『ウルトラマン』とかつて人気を二分していた手塚治虫原作の実写怪獣特撮物(企画していたのは鷺巣詩郎のお父さん)で、たびたび特撮物からの影響を語っていた完さんだが、ここでは原作漫画からのインスパイアが強いYOU THE ROCK☆のリリックがとても面白い。この時期おたく趣味ってラッパーにとってまだまだダサいと扱われる表現だったはずだが「四次元跳躍法少年画報/特殊音波狙うゴアの野望」など単語の使い方がクールに決まっている。手塚トリビュートコンピに収録されたこのバージョンと違い、アルバムでは派手な音が減り、ぐっとアブストラクトな仕上がりになっている。
スピリチュアルに傾倒していた『ARTMAN』の路線も引き継ぎつつ、『HELLO』はニューウェイヴの要素が濃くなってきている。かつて本人が所属していたバンド・東京ブラボーのセルフカバー(なんでもFat Boy Slimから影響受けてやることにしたとか…)から始まるが、これがボーカルをケロ声に変調させておりすっげえ違和感あり、何故そうしたのか謎だ。本人の肉声が出てくるのは4曲目のドラムンボッサ『Wonder Walk』からだ。
この上に上野耕路の作るヒップホップ(さすがにビートは足しているが)!、EYEとのユニットSOUND HEROによるフィーレココレージュ、電子音が飛び交う八丈島郷土民謡のカバー(唄:木津茂里)、詳細不明の民族ボーカルの上に展開される小泉今日子とのデュエット曲、Money Markがブルージーなキーボードを聴かせる『ひとつ』(東京ニューウェイヴバンドの”自殺”がカバーした山口冨士夫の曲をさらにカバー)…などといったこの人でしか成り立たない異常なトラックが並ぶ。もしかしていまだにサブスクにも動画に上がらないのはハイブロウにも程があるからか…!? まさに1990年代末の怪作だ。
VA/Cheap. 1993-1998
洋楽にお金を払うのが希少価値になってきている昨今、ほぼ見なくなったタイプの企画盤がある。”日本独自のレーベルコンピ盤(サンプラー)”だ。まだまだ日本ではよく知られていない海外のクラブ文化と音楽を流通するべく、2000年代中期までは日本のレコード会社独自の選曲(著名アーティストやライターが選曲する場合もある)に、解説文が付いてパッケージングされていたわけだが、今現在だといとも簡単にサブスク内にリストが作れてしまうため、レコード会社はわざわざそんな役割を負う必要が無くなってしまった。このレーベルが何処の国の誰々がどういう発端ではじめたとか、そういう情報も今やネットで検索すればだいたいわかる。だが、発売当時この盤がどういう扱いだったのか、今は雑誌も少ない分(あってももうみんな知ってて好きなもんしか取り上げないので)、ただでさえ情報の少ないアーティストはより掴みづらくなってしまうだろう。
というわけで、中古CD屋に行くとなるべく国内企画編集盤を探して買うようにしてるわけだけど、今回紹介するのはその事故的な一例。

今年に入って中古でこのどちらかを買い、上記の那由多マルクスのレビューを見たかどうだか忘れたけどもう片方もamazonで取り寄せた。
詳しく書くとこの<Cheap>はオーストリアのテクノレーベルで、レーベル5周年記念として1998年に発売されたこの日本編集盤は青赤に分けて<P-VINE>から2種類リリースされており、通称青盤『Cheap. Have A Cigar, My Friend.』はラウンジ/ジャズ系のサンプリングが濃く、赤盤『Cheap. Five Years In Satan’s Ass』はミニマルテクノ色の強い内容のため、(那由多の言う通り)青のほうが若干聴きやすい。双方ともにクラブユースのため全体的にはどれも地味なのだが、ミニマルをやろうがブレイクビーツやDUBをやろうが音使いが奇妙で独特だ。

さてライナーの話に移ると、解説はこの手の音楽にはおなじみ佐々木敦さんで、双方ともに全文同じだ。だが謎な事に、ここでは2枚の違いがあまり説明されておらず、明らかに佐々木さんは片方青盤のみを前提として文章を書いてしまってる。もしかして佐々木さんは2枚分の文章を書いたのに手違いで両盤ともに同じ文章が載ってしまったのだろうか?
…ここで佐々木さんが担当した解説文を集めた書籍『LINERNOTES』(青土社刊/2008)を開いてみよう。赤盤のライナーも書いていた場合はこの機会に載せていたはずだし…すると、こちらにも青盤のレビューしか載っていない。これは当時のP-VINEの担当さんと佐々木さんとで明らかな行き違いがあったのではないだろうか。担当は2枚分共通で注文したのに、佐々木さんに片方のみと勘違いされてしまったか、それとももう片方別のライターに発注していたにもかかわらず、さまざまな事情で上がらなかったのか…今現在のようにパソコンでメールをやりとりをするにもまだまだ送れる容量が少なかった90年代末の話。佐々木さん本人もたぶん記憶に残っていないだろうし、もっとも判明したところで、だからどうしたという感じですが…。
なお、1990年代テクノ繁栄期に現れては消えていったレーベルを尻目に、<Cheap>は今もってマイペースに活動を続けており、なんと今年に入ってサブスクやBandcampでほとんどの音源が再発された。日本のTake Rodriguezもそのラインナップに入っており、許可取って無さそうなのだが…いいのか、本人とっくに居ないし。
というわけで、<Cheap>のこの日本盤コンピ2枚の収録曲でプレイリストにしました。
CD収録曲中、未サブスク化であるRobert Hoodの2曲を除き、12曲目まで青盤、13曲目からは赤盤です。
かく言う私も当然<Cheap>の全ての曲を知らないので、ここにあるよりもっといい曲あるかも。
◎追記(12/1)▶︎▶︎
那由多からDMが。どうやら赤盤のライナーは当時佐々木さんと同じくHEADZの所属だった原雅明(現Rings)さんが書かれていたらしい。しかも那由多の持ってるcheapの日本盤コンピは青赤ともに原さんのライナーである事が発覚。要するにミスプリントである上にその訂正も無くまんま流通してたようなのだ。そんな事ってある!!? 初めて聞くケースだ。
原さんのライナーも読みたいので、近々那由多の持ってるどっちかと交換してもらう予定。
モンハンライズの里でかかっている曲(カムラ祓え歌)を聴いていると一青窈の『もらい泣き』、原曲ハーフテンポくらいのスロースピードでSmile.dk『Butterfly』(アイヤイヤー♪)が脳再生されてしまっていた。
しかしライズをプレイしているうちに、関連付けられて浮かんできたフレーズやメロディーから切り離されて、ライズの里テーマは里テーマ(カムラ祓え歌)として独立して記憶に染み込んだような気がする。
(だがそうではなくやはりもらい泣きやButterflyと同じ種類としてフォルダー分けされて記憶されたのか。それを知るにはまた似た音楽に出会わなければならない)
to be continued

馬渡松子『さよならbyebye』
ニチイという名の日用品と洋服が売っている複合設施設があったが、その頃にはだいぶボロくなって色あせて、数年前ほどの人の入りはなく、うちのばあちゃんのような世代の人たちが洋服を買いに行くくらいになっていた。上の階にはゲーム機が置いてあって、『バブルボブル』なんかのゲームが置いてあったが、パズルボブルはその頃すでにけっこう古いゲームで、ずっと同じ型のゲーム機が取り替えられないまま置かれていたんだと思う。そんなニチイの二階へあがる階段の前のベンチで友人と漫画を読んでいたら、ワルの上級生だちが大声でいいカモがおるわと笑いながら階段を上ってきた。このワルとはいろいろ思い出がある……。あつカネサキ!!!!!しまった!と二人とも硬直…。「お前ら何読んでんねん?コラァ」と、殴られるだけでなくカツアゲされ漫画まで取られるのかとおびえていると、「なんや、ダイの大冒険読んでんのか………。お前らええ奴やなぁ」と笑ってくれて、じゃあなとそいつらは古びたゲーム機で遊ぶためにフロアへ消えていった。ダイの大冒険を読んでいたのでカツアゲから逃れられたのだった………!!!
ということで新しくなった『ダイの大冒険』観てます。最初の方は改変部分におこでしたが、とりあえず前回放送が終わってしまったとこらへんまで進んだので、今回はラストまで制作してほしい。改変でまさかポップがメガンテしないストーリーなのかと思ったけどちゃんとメガンテしてよかった……メガンテしてよかったって何だ。泣きました不覚にも。メガンテして竜の血を飲みギラで一片の花びらを燃やしてしまうことなく、指先の一点に魔法力を集中し、花びらの中心に小さな穴をあけるほどの魔法使いになるのでメガンテしないわけにはいかないのです…が…
子供の頃はお小遣いが少なかったので毎週ジャンプを買うことができずコロコロコミックで育ち、もちろん漫画全巻買うことも諦めていたので、友達がくれた図書券でダイの13巻だけ買って、それを何回も読みました。(その後その友人からはやっぱり図書券かえせと何度も…)
13巻のアニメ化が楽しみ。しかしOPとEDはいかがなものかと…まず「生きるをする」っていうタイトルが~…(その後慣れ・OPはこれなんだとフォーマット完了…)
アニメの中身は戦って強くなってまた更に強力な敵が現れて強くなるという単純なものだったとしても、幽遊白書のOP・EDなんかは、アホな男子児童だちになんとも言えない気分を味合わせていたと思う(味合わせることに成功させていたと思う)。特にED曲の『さよならbyebye』なんて。大人の別れの曲を聴いて、まだそれを体験したことがない子供たちがその体験を想像して感じる気持ち。なぜかそれがわかるような気がする、そんな経験をいつか自分が体験するのかな、するのだろう、その時どんなことを感じるんだろう………と。そんなふうに考えて聴いていた自分は感じやすい子供だったのか?
いま子供たちがTVでアニメを観るというのが当たり前でない時代にあって、90年代と同じではないにしても、子供の感性をえぐるような、ちょっと残酷かもしれない大人の気持ちを感じさせるようなOP・EDが使われているアニメがあるなら知りたい。
いま聞き返してみると歌い方や声質はやはり違うのだけれど、パイナップルの『Diamond Crack』を最初に聴いたときは、幽遊白書の歌の人の声でこんな世界あるの?!って驚いた。ちょっと例えが違うが灰野敬二がカヴァーしている堀内孝雄『君の瞳は10000ボルト』を聴いたときのような……この声質でこのうたの世界があるのかと驚いたのでした。ほかにあれば聴きたいな。この時の馬渡松子の声に近い曲。ここのところの気分としては『ホームワークが終わらない』だけど……。



Houseside / E.S.P.

渦巻く轟音が螺旋を描いて上昇し、その発光があたりをビカビカの蛍光色に染め上げる下重守のギター。ダビーな音響処理も絶妙に、重くタイトなリズムを刻む神美長ヒロキのドラム。そして、現在はOOIOOのベースや坂本慎太郎のバンドのベースとしても活躍する本田アヤの低くうねるベース。で、何より彼女の歌である。音の壁と静寂の隙間を漂い、つぶやくように言葉を並べ、楽曲に儚くも美しい彩りを与える憂鬱な光沢。
北村昌士プロデュースの元、彼が主宰したSSE COMMUNICATIONSからリリースされたハウスサイドの93年ファースト『E.S.P.』は、その2年前にリリースされたマイ・ブラッディ・ヴァレンタイン『Loveless』の影響もひとつ感じられるのだが、そんな例えや想像をはるかに超えるまばゆい高みと、とめど尽きせぬ泉のごとくあふれ出る超感覚的知覚体験の誘惑にこちらの官能も鋭く尖りまくる。
シュガーコーティングされた甘くておいしいノイズにポップさも散りばめたこのファーストと翌94年にリリースし、より遠く音響的でトランシーな世界を完成させたセカンドにしてラストアルバム『Mindwar』。この2枚はリリースから30年近くの時を経たいまも、プリズムの板を通しているかのごとき虹色の強烈な光と幻想的かつ独創的なサイケデリアで私の全身全霊をくらくらと包みこんでくれる。
〜余談〜
東京からハウスサイドがやって来るということで、94年に十三ファンダンゴで私が唯一体験したハウスサイドのライヴ。下重の耳をつんざくギターワークの繊細で天才的なひらめきときらめきを確認するとともに、曲をぐいぐい先導して太くバキバキ波打つアヤのベース、そして、轟音マインドウォー・アンサンブルに埋もれてほとんど聞こえてこなかった……声と佇まいの危き可憐さに恍惚とした当時の空気がぶわーんと蘇る。
京都のジーザス・フィーヴァーとの共演なんていまやおとぎ話のような組み合わせだったのだが、ジーザス・フィーヴァーのドラムのチャイナが、そのまま続くハウスサイドでもサポートとしてドラムを務めていたのは二度見どころか、演奏の終わりまでというか、家路の途中もというか、いまだに目を疑う光景なのだが、あれは私の夢だったのだろうか?

HI-SPEED / 8BIT FEVER
『デザインあ』などのテレビ番組でCGアニメーターとして活動するミズヒロ・サビーニ(※日本人です)を中心としたバンドの2作目で、佐々木敦の<UNKNOWNMIX>からリリースした1st(1996)はレコメンテッド系のプログレッシヴ・ロックバンドだった(プロデュースは『キルミーベイベー』などでおなじみEXPO/マニュアル・オブ・エラーズの山口優)。その後全編電子音楽のソロ作を経て3年越し、そこそこ大所帯だったメンバーを3人に減らしての路線変更。ここまで変えるなら名前も変えて活動するだろうし、2021年の今だったらありえない。
そもそも何故このバンド名なんだろう? 1stはその名前ほどのスピード感はあまり無く、むしろ脱力感が全体を支配している。そして、そのムードはこの2ndでも変わらない。
(ひと段落はしていたものの)テクノもヒップホップもまだまだ太く重くハードエッジな路線を突き進んでいたのが1990年代後半のクラブシーンだったが、その一方でAir、<Rephlex>のGentle PeopleやLuke Vibertなどのモンド/ラウンジミュージックと言われた1960〜70年代の音源をサンプリングをする者、一転してDMX Krewや<CLEAR>のClatterbox、そしてDaft Punkなど、この数年前まではダサイものとされていた1980年代オールドスクールエレクトロを基調とする、軽快で色鮮やかなサウンドを指向するアーティストが現れはじめていた。
ドイツでは<Bangalow>やMouse on Marsが、日本では砂原良徳やFantastic Plastic Machine、<Daisyworld><Transonic>などもそれらに呼応するかのような作品を次々発表する。そしてその中にこの盤も存在していた。
本作は1960〜70年代モンド/ラウンジ的な音源をサンプリングをしながら、楽曲自体は1980年代的チープなエレクトロ・ハウスというスタイルを取り入れている。
当時の熱心なテクノファンに食ってかかるようなURのサンプリング#2、レイヴものを模倣しつつベース音が全くない#10、<COMPAKT>ライクなミニマルから一気にゆるふわトランスに変わる#8など、当時としても歪なトラックが多く、収録曲の半分ぐらいは3分強で終わる。あまりにも突飛だった本作、20年経った今ならそれでこそパソコン音楽クラブなんかと同列にも聴けるのではないだろうか。ただ、今みんなが大好きなシティポップ/フュージョンっぽさは全くないけど…(そういう意味では1980年代のグラフィックを模倣しているSynthwaveとも趣が異なる)。
さらにこのアルバムが特異なのは、テクノレーベルではなく、小林弘幸のオルタナティヴロックレーベル<HOT-CHA>からのリリースであったこと。ロックバンドのくるりがDaft Punkに感化され『TEAM ROCK』でハウスを制作するのはこの2年後、今みたいになんとなく4つ打ちを演奏するようなバンドもまだ多くは無かったはず。メインの楽曲である#3には、Corneliusと結婚する直前の嶺川貴子がボーカルで参加している。
その後このユニットは程なく分裂、ミズヒロさん以外の2人はDEAVID SOULとして<Transonic>から1980’sディスコを極端に誇張した傑作アルバムをリリース、SEGAのゲーム『ジェットセットラジオ』にライセンスで収録され全世界のゲームファンの耳馴染みになり、現在までに断続的に活動している。
ミズヒロさんはその後、何故かワープハウスのアルバム(こっちのほうが本当の意味でHI-SPEEDじゃないか!)を突然リリース、長いブランクを空けて2010年代にカセットテープレーベル<吟醸派>を立ち上げ、本人の変名はもちろんサワサキヨシヒロやhakobuneなどをはじめ世界各地からのニューエイジ/ドローンを多くリリースしていく。
その数多い本人の作品のうち”Portopia’81″名義のこの1作はVaporwaveレーベル<Adhesive Sounds>から2015年にリリースされ、私はこの作品を『新蒸気波要点ガイド』でも取り上げさせていただいた。かつて神戸で催された大規模な博覧会をその名に冠したこのユニットはニューエイジ的な電子音楽だが、ちょっとだけHI-SPEED名義のあの盤の愛嬌さが見え隠れするところが嬉しくなるのだった。