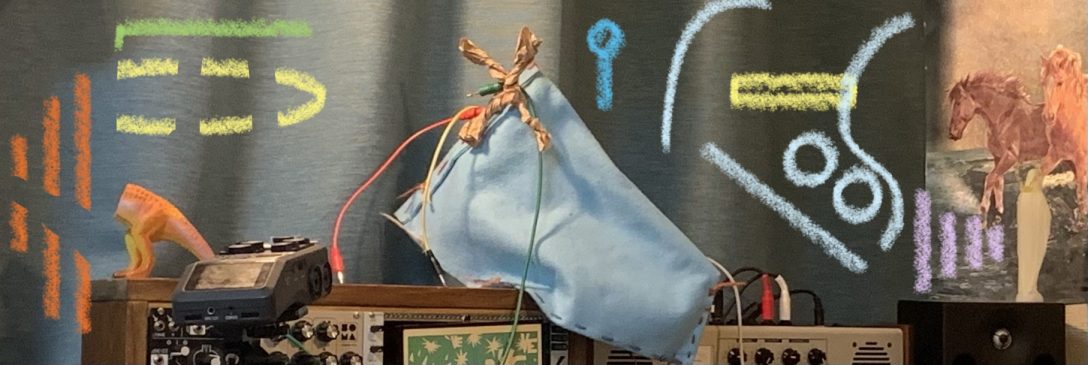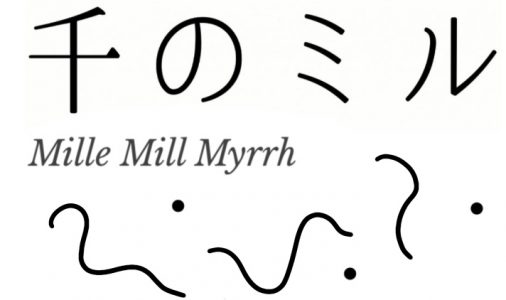2018年に円谷プロの特撮ヒーロー番組『電光超人グリッドマン』(1993)の続編がアニメ化すると聞いたとき、一部の特撮マニアを除いて期待の声はあまり多くはなかったはずだ。電脳空間を舞台に怪獣の姿形をしたコンピューターウィルスと戦う電子生命体…といった世界観は今観るとちょっとだけSynthwave的で、その発想はインターネットの普及より数年早かったものの、そのサイバーワールドの描写も話の展開も正直大味だし、誰にでも進められる傑作ではない。が、(この作品では怪獣を作り出す側の)少年の異常に情緒不安定な心の描写は『新世紀エヴァンゲリオン』(1995)にこれまた2年早かった。
『SSSS.GRIDMAN』(2018)は『新世紀エヴァンゲリオン』(1995)でおなじみとなったGAINAXから独立したTRIGGERが制作したアニメで、ご覧の通り日本のいかにもなアニメーションの画風で着ぐるみ+ミニチュア特撮を『シン・ゴジラ』(2016)以降のCG技術を駆使して披露、それだけなく同じ円谷作品…それも旧来の怪獣特撮マニアからは比較的軽視されがちだった平成ウルトラマンシリーズからの文脈のサンプリング的引用を随所に散りばめ、『エヴァ』の先祖返り的アクロバットなメタ展開をやってみせた傑作となった。
そして本作の劇伴を担当したのが、『エヴァ』『シン・ゴジラ』と同じく鷺巣詩郎さんである。
『エヴァ』の庵野秀明監督が特撮ヒーロー物、特に『ウルトラマン』シリーズの影響が強い事は、ここを見ている方々もご存知の事だろう。鷺巣さんの親御さん・鷺巣富雄は円谷プロの競合他社として1970年代に『宇宙猿人ゴリ対スペクトルマン』『電人ザボーガー』など多くの特撮番組を手がけたピー・プロの創業者で漫画家でもあり、物心ついた頃から特撮に(裏方の側からも)慣れ親しんできた事が各所で多く語られている。
本作劇中、主人公たちの日常シーンではほとんど劇伴がかからない。1話の前半ほぼ日常音と声のみで話が展開されるのは、鷺巣さんの要望でもあったという。これについてはこちらのインタビューでも語られているが、東宝『ゴジラ』をはじめとする初期の怪獣映画が通常の生活シーンでは極力BGMが抑えられている事にも起因しているようだ。
さて、今回主題にしているのは主題歌ではなく、その劇伴曲。全12話中折り返しの第6話、突然主人公の前に現れたとある人物の口から、自分達の住む街にどうやって怪獣が現れるのか、その秘密が打ち明けられるシーン。ここに挟まれるいかにも1990年代的な粗いポリゴンCGとともに、大々的に使用される少し牧歌的なテクノトラック。
劇伴はこの楽曲のバージョン違いが多くあり、SMAPなどの仕事でおなじみCHOKKAKUがアレンジを担当するEDMバージョンもあるが、このオリジナルはあくまでテクノでなくテクノポップを意識しているという。1980年代から歌謡曲の仕事を多く手がける鷺巣さんならではの発想だが、図らずしてSynthwaveになっているようでちょっとBPMが140と早い(ということは、ピッチを遅くすればまさしくSynthwaveになる)。
思い出してみると、旧『エヴァ』のサントラにちょくちょくR&B曲が挟まれており、鷺巣さんが同時期にMISIAなどのプロデュースを手掛けていた事を考えると自然ではあるが、当時はエヴァのようなオタク系アニメとは相当に水と油だった印象がある。
で、本作の好評を受け制作されたシリーズ続編『SSSS.DYNAZENON』が、今2021年夏に全話放送終了したばかりだ。そう、この『SSSS.DYNAZENON』にもこの手の英詞曲が収録されていて、しかも劇中超いい感じに挟まれるわけだ(下のPVを参照)。肝心の曲調もどこかMTVを彷彿とさせる、擬似の90s洋楽というか…当時だったら首を傾げていたような洋楽風の楽曲が、時代も一回りしてようやく違和感が無くなったわけだ。