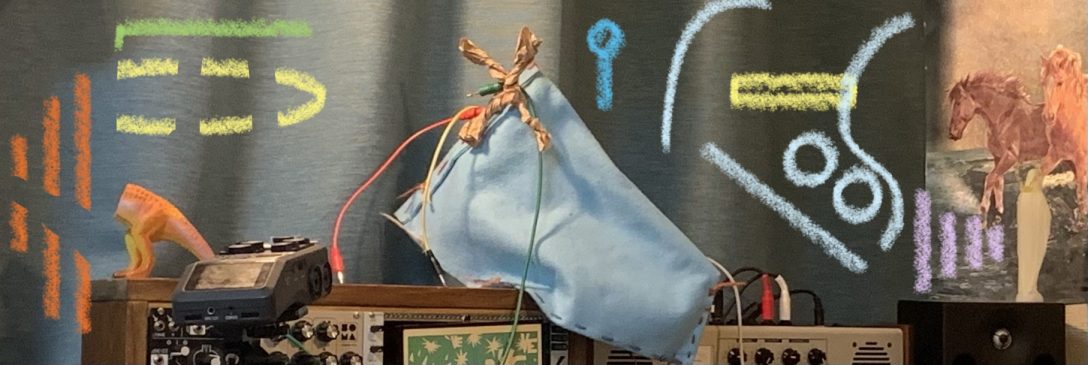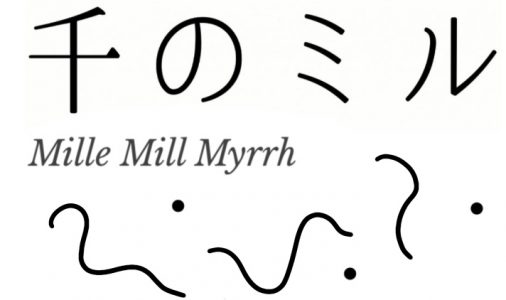2021ベスト、の名の下に
やっと終わった…
もう2021から1ヶ月経過、数年来取り組んでいたguitar viol製作(改造)が電化に課題が残るがやっとほぼ終了、そろそろ次のステップに行きたい。
さて昨年を振り返ってみるか、と。しかし、

昨年中も意識的に音楽を聴いていたでもなく、戯れにele-kingとか手に取るとこんなに収穫多い年だったんすか?ほんと?と思いますわ。シティポップ云々も今更でだから何?としか思えず、アナログ価格の高騰の呼び水となって迷惑、としか。
リスニング習慣が旧態かつ旧世代で記憶力が減退しているので、モノ→所有のステップ抜きでのサブスクやデータ拝聴では聴いた時点でのいいなこれ!の後は記憶に残らず、モノ所有してても聴かずに放置してたり、1度しか聴いてなかったり、聴いても忘却してたり、よく聴いたものでもあのジャケの何曲目ぐらいとか曖昧な記憶ばかりでして。
ですんで、小手先での2021雑感としてお茶を濁すべく、棚に整理されずにその辺に雑多に積まれてるCDとレコを列挙してみたら以下のように。
【CD】 下記以外にも過去作等々買ってるが昨年もの中心に

JUANA MOLINA/ANRNAL EN VIVO EN MWXICO
10年以上前ロンドンの教会でライブ見た方、自分にとって久しぶり。変拍子の曲への消化の仕方が上手い。リズム解釈が自然で変でかっこいい。アルゼンチン音響派から随分経ったな。
69th world/yXIMALLOO
師匠たしかWindows98のPCで作ってるはずなんだけどどうやってこの音出してるんだかわかんねえ。面白い。
PERSONA/PERSONA
ブラジルのヒタ・リーのバッキング演ってた人の70年代再発。まあジャケほどのインパクトはない。

NILS FRAHM/OLD FRIENDS NEW FRIENDS
これはジャケ最高に好き。2枚組CD1枚目は物音と弱音ペダル踏んだピアノの音のバランスは好き。
VANISING TWIN/THE AGE OF IMMUNOLOGY
これじゃなくて最新盤があって良かったんだがすぐ出てこない、どこ行った?
あ、これだ、
VANISING TWIN/GEKKOU
良かったはずだが聴き込まぬまま年が明けた。改めて聴かねば。

1000円再発CDブラジルシリーズ何枚か
良いのたくさんあったがこれ以上の列記は控えとく
Anna Yamada/MONOKURO
もう天才。好き。アナログモノシンセ弾き語り。音程が素晴らしく良い伸びる声。

考える目/斉藤友秋
うまくて嫉妬する。
Satomimagae/Hanazono
素晴らしい。素晴らしすぎる焦点に絞られてる感じが却って物足りなく感じないでもない。
SAM GENDEL/inga2016
御多分に洩れず好きなんだが、一挙にたくさん出すぎて追えてない。

MIMIC WORKS/杉林恭雄
後述
INOYAMALAND/Trans Kunang
俺は1stのDANJINDONPOJIDONリアルタイムで好きなんだよ、自慢。もはや普通のカシオトーン弾くだけでもアンビ足り得る山下康に憧れる。

Phew/New Decade
カッコいい!もうこれは外せない、特に2曲めまでの感じと最後の前の曲だったっけな?何回も聞ける。凄い人。で話すと気さくな感じがまた素敵。いや話したことないけど。立ち姿がまた凛としてかっこいいの。
MIHARU KOSHI/VOYAGE SECRET
こちらも屹立し年齢超越したキュートネス&隠しフレンチエロスの孤高のお姉さま。
フレンチもいいがオリジナル曲の独自さはこの人しかできない世界。
Brian Wilson/At My Piano
これを忘れてはいけない。ビーチボーイズの名曲の数々を、ピアニストなわけではないブライアン自身のピアノ演奏で聴かせる歌の無いインスト作品。当然アンビエントでも音響作品でもないです。でもほんと好きな作品です。これからも何回も聴くと思います。
【レコード】 下記は再発を中心に。中古で買ったフランス現代音楽やハワイアン等々も良かった。

PALE COCOON/繭
金沢の80年代デュオ?の再発。昔ソノシート持ってた。ピアノラレコードの人に勧められて買ってみた。すごくいいとまでは思ってないんだが。
斉藤友秋/はじめからここに
上手くて嫉妬する…
robert mills/related ephemera
これは何回も聞いたがすごく良かった気がする。また聴かねば。SP盤等の音から再構築してるが、酩酊(後述)なんかとはレベルが違う。いい。

BOBBY BROWN/THE ENLIGHIETING BEAM OF AXONDA
犬を抱いて海辺で自作楽器に囲まれてるジャケが印象に残るサイケ名盤のひとつ、のどういうわけかアナログ再発。思ったよりずっと素敵。また聞き返さねば。
BRIGiTTE FONTAINE & ARESKI/Theatre Musical
73年に制作されていたものの再発だが、未発表?だったんだっけ?すごくいい。大好き。
After Dinner/1982-85
CD持ってたけどアナログ再発。CDで聞いたよりずっと印象が深い。横川理彦さんも参加していたこのグループ、マッドエンジニアの宇都宮泰さんの音響工作がクる。何度も聴かねば。
MONO Fontana/cribas
アナログ出たんで買ったけど、前に発表されてたよな確か。これも良かったわ。また聴かねば。

番外)酩酊/サード、かなんか。
SP盤のサンプリングで再構築した失われた日本の音風景つう立脚点に興味を持ち、試聴し気になり購入したが、広義のヒップホップマナーの先までは立ち入っておらず、大昔に第三世界の音楽を表層だけ取り入れたワールドミュージックもどき(なんかディープフォレストとか…)に聴くような植民地主義?とか浅めのエキゾシズム?とかの印象を聴くほどに感じた。俺には合わず。なんかイヤ。
最近でもっともスゲーと思ったのは、知り合いの森氏のシネルパの音源をネットで聴いてたときに途中からアトーナルな電子音がカットインしてきた時で。
え?シネルパってこんなに凄かったか!さすが山我静さんポラリス(シンセ)こんなふうにも使うのか!と思ってたら、同時に繋がれたCDデッキ内のくじらの杉林恭雄さんがsystem100で製作した初期電子音楽集が勝手に鳴りミックスされてた様子。曲に寄り添わない偶然のミックスの意外性が一番面白かったし、自分の制作する音楽も完成!と思うより前の有象無象の妄想状態が一番面白いのでは?とも思う。
結局、現存する作品よりも偶然の組み合わせに遭遇する新鮮さや、夢想する脳内にある形なきモヤモヤしたもの、何ら因果なき新鮮さに出会いたいといつも思っている。脳内のモヤモヤは消費できないし言語化できない。
それと自分内に無かったものとの出会いが70〜90’s半ばに活動した映像作家の中村雅信さんの音楽と映像のリズム感が最高だった。差異のある反復映像が繰り返されその映像リズムが音楽と相まってもう映像版ミニマルミュージックで圧倒的、多重露光の複数時間並存する作品も素敵!音楽も既存のレコードの最終溝のループ音他をオープンリールテープで回転数変えたりして自分で作成編集したのとかも使っていて新鮮なものとして聴いた。
わたし文章長くなりがちなのに大量のテキスト追うの好きでなく、またテキスト表現も好まず、なのでモコモコさんの連日の投稿も一瞥しただけでもう追う気がなくなるし、ほかの方々の年間ベストもサラッと読めばまだいい方で、読んでも読んだそばからすぐ忘れてしまう。自分の投稿(中断中)も基本ワークショップでの受講録を記してるだけ。映画も文学も自作の歌詞もみなストーリーや明確な脈絡あるものではなくどこかに跳ばされる恍惚と愉しみに淫するのが好きで、語ることばを持つ方々にはコンプレックスとルサンチマンばかりでしてどうも。
俺はさあ、ギターを最初はさだまさしやアリスでおぼえて嬉々として弾いてた中坊から始まったんだぜ、最低だよなもう。だから語るべきものなんて何にも無いんですよ、ねえ。

今日は異常に靴下が下がる病いに冒されてしまいたいへん難儀した。
少し歩くとまもなく靴下のかかと上部分がみるみるかかとの下へとずり落ちてくるのだ。そのため頻繁に立ち止まりずり落ちたのを上げねばならず、済まして歩き出すとまた直ぐにずり落ちてきてまたそれを…の繰り返しなのだ。何もかもこんな調子なのか俺は、と嫌になる。
誰が読むんだこんなの。