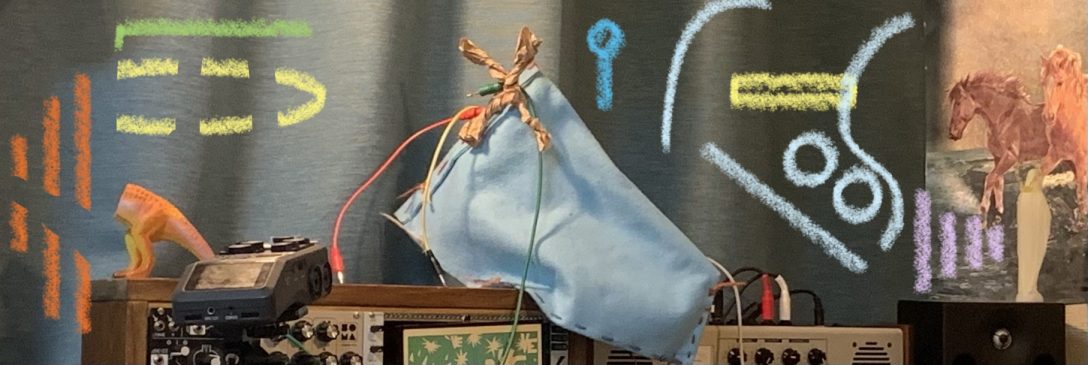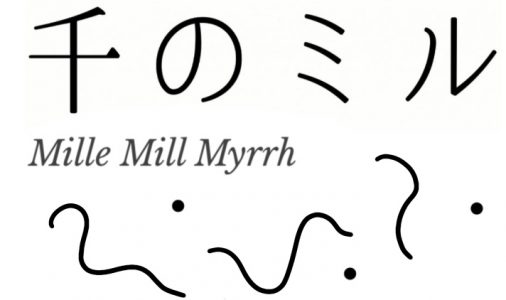ーかた子の日記ー
すべての人間がスタンド能力を使えるようになった世界では、『矢』はただの武器になる。
「もしかして……」
ぼくはふと思いついて、自分の身体を見下ろした。
胸元から腰までを覆う黒いシャツ──その上には、細い革ベルトが巻かれている。その先にぶら下がっているのは、一本のナイフだった。『矢』を刺されたとき、同時にこのナイフで刺し貫かれたのだ。
「…………」
今さらながらに、ゾッとする。あれだけ深く突き刺さったというのに、今はもう痛みすら感じない。まるで、怪我などしていなかったかのように。
「でも……どうして?」
あの『矢』には、不思議な力があった。
ぼくの体内に侵入した瞬間、それは一瞬にして心臓と同化してしまったかと思うと、直後にはまったく別のものへと変わっていた。
スタンド能力──しかも、超自然的な力を秘めたものへ。
だが、それならどうして、あんな風に刺されなければならなかったのか?
「いや……違うな」
考え直してみる。
ぼくが受けた傷は、確かに致命的だったはずだ。
にもかかわらず、こうして生き延びている。ということはつまり……。
「治っているんだ!」
自分の胸に手を当ててみると、鼓動に合わせてドクンドクンと脈打っていた。
「いったいどうやって?」
疑問を口にしながら、ぼくは自分の身体の変化について考えてみた。
そういえば、あの『矢』を受けたときも、奇妙なことが起きた。
最初は、何が起こったのか分からなかった。突然、全身に激痛を感じたと思ったら、次の瞬間には嘘のように消えていたのだ。
まるで、夢でも見ていたかのような感覚だったが、実際にナイフによる傷跡は残っているし、服にも血痕が残っている。何より、あのときと同じ場所に同じ傷を負っているということが、これが現実であるということを証明していた。
「だとしたら……」
どういうことだ? なぜ、ぼくだけが助かった? 他の連中だって、あの『矢』によってスタンド能力を得たはずなのに、誰一人として死んではいないじゃないか。
「まさか……!?」
ぼくは、ハッとした。
スタンド能力は、精神の力だ。
もし、スタンド使いを生み出すものが本当に存在するとすれば、それは人間の精神そのものということになる。
そして、ぼくたちは今までずっと、スタンド能力というものが単なる特殊能力の一種だと思い込んでいた。超能力者なんてものはテレビの画面の向こう側にしか存在しないものだと思っていたし、そういうものだと決めつけていたのだ。
しかし、実際には違った。
テレビの向こう側の人間だろうと、超能力者だろうと関係はない。
人間は皆、生まれつき『スタンド能力』を持っているのだ。ただ、それを自覚していないだけで。
その証拠に、先ほど見た光景を思い出す。
『矢』を射られた直後、ぼくたち全員の身体に変化が現れた。
まず、全員が激しい頭痛に襲われた。続いて、胸の奥から何か得体の知れない力が湧き上がってくるような錯覚を覚えた。
あのときの症状を、もう一度思い出す。
胸の辺りから発生した力は、やがて脳に達して全身に行き渡った。そうすると、今度は逆に頭の中から力が抜けていき、代わりに身体中の細胞が活性化していくのを感じた。
あの感覚は、間違いない。
あれこそまさに、スタンド能力が発現した瞬間なのだ。
「じゃあ、やっぱり……」
ぼく以外の連中は、すでに死んでいるということなのか? あの『矢』で射抜かれた瞬間に、生命活動を停止させてしまったというのか?「そんな馬鹿な」
否定したい気持ちとは裏腹に、ぼくは嫌な予感を覚え始めていた。
今さらながらに、自分がとんでもない状況に置かれていることを実感する。
「とにかく、ここから逃げないと」
ぼくは呟くと、立ち上がった。
幸いなことに、手足の痺れはほとんど取れているようだ。これなら何とか動けるだろう。
「でも、どこへ行けばいいんだ?」
途方に暮れてしまう。
ぼくが目覚めた場所は、どこかの建物の中のようだった。床にはカーペットが敷かれていて、壁には豪華な装飾が施されている。かなり大きな部屋だが、家具らしいものは見当たらなかった。天井からはシャンデリアのようなものも下がっているが、電球は点いていない。
どうやら、この屋敷の主人は相当な金持ちだったらしく、家財道具もほとんど持ち去られてしまっているようだ。
「……」
ふと、ぼくは部屋の片隅に置かれたものに目を留めた。
一見したところ、それは大きなトランクケースだった。
ただし、普通のトランクではない。鍵穴もなければ取手もない。ただ、蓋の部分に大きなダイヤル錠がついているだけだ。大きさは、ちょうどぼくが横になったぐらいだろうか。「……」
ぼくは無言のまま、その前に立った。
そして、ゆっくりと手を伸ばすと、ダイヤルを回してみる。
カチッ。
軽い音がして、ロックが外れた。
「開いたぞ」
ぼくは声に出して言うと、そっと蓋を持ち上げてみた。
中には、何も入っていなかった。「え?」
ぼくは呆然としてしまう。
慌てて、周囲を見回すが、やはり他には何も見当たらない。
「どういうことなんだ? これは」
戸惑いながらも、ぼくはその箱の中に潜り込んだ。
まるで棺桶のような狭さだ。ぼくは膝を抱え込むようにして、その場に座った。
しばらく待ってみたが、特に変化はなかった。
「誰かいないのか!?」
大声で叫んでみるものの、返事はない。
耳を澄ませても物音ひとつ聞こえず、静寂に包まれたままだ。「ちくしょう!」
ぼくは思わず毒づいた。
ここは、いったい何だっていうんだ? どうして、こんなところに閉じ込めておく必要があるんだよ!
「……」
そう考えた途端に、ぼくはあることを思い出し、ハッとした。
そういえば、さっき『矢』を射られたときに聞いた言葉。あれは何と言っていたか。
確か、こう言ったはずだ。
──お前たちの身体には、既に『矢』を埋め込んである。
──その『矢』は、特殊な力を持っている。
──『矢』を使えば、誰でもスタンド能力を得ることが出来るのだ。
「……」
まさか、と思った。
だが、そうとしか考えられない。
つまり、ここに囚われているのは、他の仲間たちだということなのではないか? そして、ぼくだけが助かった理由というのは……。「うわっ!?」
突然、目の前の空間が歪み始めたと思うと、そこに巨大な人影が出現した。
いつの間に現れたのか、そこには一人の男が立っていた。
年齢は四十代後半といったところだろうか。髪は薄くなりかけているし、口元にも髭が生えている。しかし、何よりも特徴的なのは、その恰好だ。上半身は裸で、下半身にも布地のようなものは一切身に着けていなかった。それだけならまだしも、男の身体には奇妙なものが生えていた。
それは、人間の身体の一部ではなかった。
植物の蔓のようなものが複雑に絡み合ったもので、一本の太い幹から幾つもの枝が伸びて、それぞれが独立した生き物のように動いているのだ。
ぼくは、その男のことを知っていた。
つい先ほど、夢の中で見たばかりなのだから。「ジョ、ジョナサン・ジョースターさん……」
ぼくは掠れた声で呟くと、震える指先で相手の顔を差した。
そう。
その男は『矢』によってスタンド能力を得た、最初の一人にして最強のスタンド使い。『矢』を作り出した張本人であるDIOの息子であり、ぼくの祖父でもある人物だった。
11
「久しいのォ~、花京院よ」
老人はニヤリと笑うと、ぼくの名を呼んだ。
「お、おじいさん。あなたは、本当に……?」
「何を驚いている? わしの顔を忘れたか?」
「忘れたなんてもんじゃないですよ。だって、そんな姿になっているなんて、想像できるわけがないでしょう?」
「なぁに、心配するな。そのうちに慣れる」
「……」
確かに、慣れないうちは違和感を覚えるかもしれないが、それにしても限度というものがあるだろう。いくらなんでも変わりすぎだ。
ぼくは改めて、祖父の全身を眺め回した。頭から足まで、完全に植物に覆われている。
腕や脚の筋肉は盛り上がり、全身にびっしりと緑色の毛が密生していた。
「ところで、どうじゃ。この世界は?」
「この世界って、何のことですか?」
「とぼけるんじゃあない。ここがどこなのかぐらい、もう気付いているはずじゃろう」
「……」
ぼくは黙り込んだ。
確かに、薄々感じてはいたが、認めたくなかっただけだ。「えーと、もしかしてですけど、ここは天国とかいう場所なんでしょうか?」
「ほう。なかなか察しがいいのぉ」
祖父は感心するように言うと、ぼくの頭を撫でた。「だが、少し違うぞ。ここは天国でもなければ、地獄でもない。お前たちがいた地球とも別の次元にある世界だ」「別次元の? ということは、いわゆる並行世界だとでも言うんですか? それこそSF小説みたいな話ですね」「まあ、そういうことだな。もっとも、お前たちの世界の人間にとっては、こちらの世界のほうが遥かに現実味のある存在かもしらんが」「……」ぼくは混乱してきた。
まったく、何が何だか分からない。「ええと、ぼくは死んだんですよね? それで、神様に会わせてもらえるとかいうことではないんでしょう?」「そうだな。まずは、そこから説明していこう」
祖父は静かに語り出した。「実は、お前たち全員が死ぬ前に、わしは一度、お前たちと会っている」
「えっ?」
「といっても、今のお前たちは、その時の記憶は残っていないはずだ。わしも、この姿になって初めて、自分が死んでしまったことを自覚したぐらいだからの」
「それは、どういう意味ですか?」「簡単なことさ。わしが死んだとき、魂だけが抜け出てしまった。肉体は滅んだものの、精神だけは生き続け、やがて他の生物に取り憑いて、新たな生命として生まれ変わることになる。これが、俗に言われる『幽体離脱』現象だ。ただし、その際に記憶はリセットされるので、以前の自分を思い出すことはない。それが普通だ。しかし、わしの場合は、その逆だった。魂だけの存在になったわしは、他の生物の中に入っていき、その身体で生活しながら、少しずつ前世のことを思い出していったのだ。お前たちには、わしの声は聞こえなかったが、お前たちの身体の中には、常にわしの精神の一部が宿っていた。つまり、お前たちの身体を通して、わしはお前たちの生活を垣間見ていたのだ」
「……」
「さすがに驚いたな。まさか、自分の孫の中に、DIOの息子がいるとは思わなかった。しかも、そいつがスタンド能力を身につけたのは偶然ではなく、わしのせいだというではないか」
「……」「わしは、お前がDIOの息子であることを知っていた。そして、わしの魂の一部をお前の体内に埋め込んでおいたのさ。そうすれば、いつかDIOを倒すことが出来ると思ってな。ところが、DIOの息子の身体には、既に別のスタンド使いが取り付いていた。そこで、わしは考えた。その身体を奪い取ればよいのではないかと。その方が手っ取り早いし、何より面白そうだったからのォ~。そこで、わしは『矢』を使って、その身体を乗っ取ることに成功した。これで、後は息子の身体を奪えば良いと思ったのだが……どうやら、わしの考えは甘かったらしい」
「……」
「『矢』を使ったときに、奇妙な感覚があった。まるで他人の意識が入り込んできたような……。おそらく、あの『矢』が作り出した『世界』の中では、互いの人格や意思が混じり合いながら、一つになっていくようだ。その過程の中で、DIOの息子のスタンド能力も目覚めたということだろう。だが、同時に、DIOの息子のスタンド能力も目覚めつつあった。DIOの息子のスタンド能力は、DIOそのものと言ってもいいほどに強力だったからな。わしは、すぐにDIOの息子のスタンド能力を封じることにした。だが、わしのスタンド能力では、DIOの息子のスタンド能力を完全に封じ込めることはできなかった。わしは、仕方なく一時的に封印するだけにとどめたのだ」「……」「こうして、わしは自分の息子に勝ったわけだ。もっとも、わしの力だけで倒したわけではない。わしはただ、少し後押しをしただけだ。お前が、自分の力で勝ち取った勝利だということを忘れるんじゃあないぞ」
「分かりました」
ぼくは素直に返事をする。「ところで、おじいさん。あなたは何者なんですか? どうして、ぼくなんかのためにそこまでしてくれるんですか?」
「お前のため? 勘違いしているんじゃあないのか?」
「え?」
「わしは、お前などという人間に興味はない。わしが興味があるのは、お前の祖父のジョナサン・ジョースターのみよ」
「じゃあ、ぼくは関係ないってことですか?」「当然じゃあないか。わしが欲しかったのは、あくまでもDIOの息子の肉体なのだ。お前の祖父が生きているうちは、いずれまた、わしの邪魔をしに来るかもしれん。だから、わしは先手を打ったまでじゃ。DIOの奴が復活する前に、わしの手で倒すためにな。だが、わしも所詮は一人の老人に過ぎない。一人で出来ることなど限られている。だから、わしは仲間を求めた。DIOと戦うための同志をな」「それが、ぼくたちだって言うんですか? でも、どうやって? ぼくたちは全員、死んだはずでしょう」「もちろんだ。本来なら、お前たちも死んでいるはずだった。しかし、お前たちは、わしが用意した『世界』に入り込み、生き延びることができた。『世界』は、いわば天国と地獄の間にある場所だ。普通の人間には、入ることも出来ない。ましてや、入り込んだまま出てこれなくなることもある。だからこそ、わしはお前たちを『世界』に送り込むことにした。お前たちならば、DIOの息子と戦えるかもしれないと考えたからだ。わしは、お前たちのことを見捨てなかった。お前たちが生き続ける限り、わしも生き続けようと思っている。お前たちがDIOを倒すそのときまでな」
「……」
「さて、そろそろ時間も迫ってきた。わしの役目も終わりのようだ。もうじき、わしの魂は再び肉体を離れ、他の生物に乗り移ることになるだろう」「ちょっと待ってください!」
ぼくは慌てて言った。「まだ聞きたいことがたくさんあるんですよ。それに、ぼくはともかく、他のみんなはどうなるんですか? ぼくのせいで死ぬことになったんですよ。なのに、このままお別れなんて納得できません」「安心しろ。わしは、この世界に戻ってくるつもりだ」「本当ですか!?」「ああ。ただし、その前に、お前にやって欲しいことがある」
「何です?」
「わしの代わりに、DIOと戦ってくれ。わしの魂の一部は、今もお前の中に留まっている。お前の中にいるわしの分身が消えれば、わしもまた消えることになるだろう」
「……」「もし、引き受けてくれるというのであれば、わしの魂の一部をお前の中に残してやろう。わしが戻って来たときに使えるようにな」「……分かりました」
ぼくは静かに答えた。「引き受けましょう」「そうか」
おじいさんの身体が輝き始める。身体が透け始めていた。ぼくは、おじいさんの身体に触れようとした。すると、おじいさんがそれを制した。「わしに触れるな!……いや、触らないでくれたまえ」
「すまない。今のわしは幽体離脱の状態だ。幽体は、精神体の一種だ。つまり、実体がない。だから、わしは、お前たちに干渉することができないのだ」
「おじいさん……。ありがとうございました」
ぼくは深々と頭を下げた。「礼を言う必要はない。わしは、お前に約束したはずだぞ。お前の祖父の代から続く因縁を断ち切るとな。わしには、その義務がある。お前は、その義務を果たした。それだけのことじゃ」
「おじいさん……。ぼくは、あなたのおかげで、生きる目的を見つけることが出来ました」「そうか……」
「ところで、おじいさん。あなたの本当の名前は、一体誰なんですか? 教えてください」「わしの名前は……」
そして、おじいさんは語り始めた。
第三部 完
「あとがき」
こんにちは。この本を手に取ってくださり、本当にありがとうございます。
さて、いよいよ三部のスタートとなります。実は、ぼく自身は、あまり『ジョジョ』を読んでいなかったりするのですが(笑)、アニメは見ていましたし、マンガも少しは読んでいましたので、大まかなストーリーの流れは把握しています。特に、第一部と第二部については、ある程度は覚えているつもりです。
ただ、今回、ぼくが書きたかったことは、承太郎やジョセフたちの戦いの物語ではありません。
本書の内容は、あくまでジョースター家の宿命である「ジョナサン・ジョースターの肉体を巡る戦い」を描いた物語です。ジョナサンの孫であり、ジョナサンの血を引くディオと、彼の配下であった花京院典明との死闘を描くことで、「ジョナサン・ジョースターの肉体」をめぐる戦いを終わらせようと思ったわけです。そのため、承太郎たちは脇役に徹してもらいました。まあ、彼らも十分に魅力的ではありますけどね。
ちなみに、今回の話は、一九八五年当時に書いた原稿を元に加筆修正したものになります。ただ、その時点では、まだ第四部が出版されるかどうかも分からない状況だったので、第五部は執筆していなかったはずなのですが、なぜか第四部から第五部にかけて、かなりの量を書いていたみたいですね。どうしてこんなことになっていたのかは、正直よく分かりません。ひょっとしたら、どこかの時点で、無意識のうちに書いていたのかもしれません。いずれにせよ、こうして出版されることになりましたので、改めてお礼を申し上げたいと思います。
さて、これから先は、しばらく「あとがき」が続きます。
本書は『ジョジョ』シリーズ初の長編小説ということになります。
当初は、短編連作という形でスタートする予定だったんです。しかし、ぼく自身が長編を書くことに慣れていなかったせいもあり、なかなかうまくまとまらず、結局、連載形式で書くことにしました。その結果として生まれた作品が『JOJO A-GO! GO!』です。
『A』は「アドベンチャー」の略です。これは、ぼくにとっての冒険を意味しています。冒険とは、常に危険が伴います。一歩間違えば、大怪我をしたり、命を落としたりすることもあるでしょう。だからこそ、『JOJO』は「アドベンチャー」というタイトルにしたわけです。
この『JOJO』は、いわば第一作。いわば序章に当たる作品です。ぼく自身にとっても初めての試みだっただけに、いろいろ試行錯誤を繰り返しながらの執筆でした。それでも、何とか形にすることができました。
そして、第二作の本作。今度は、第一部の承太郎を主人公にしてみました。これもまた、チャレンジングな挑戦です。何せ、主人公の承太郎は、主人公であると同時に、ラスボスでもあるんですから。しかも、その相手が宿敵のDIOではなくて、実の息子だというのがミソです。承太郎がどんな人物なのか? どのように成長していくのか? その辺りのところをじっくり描いてみたつもりなのですが、どうでしょうか? 承太郎の魅力が少しでも伝わっていれば幸いです。
そして、この第三部。ぼくにとっては、かなり思い入れの強いエピソードになっています。
投稿者: 那由多マルクス
虹釜太郎 / メレンゲレレ治験ジャズ
そんな感じで、この人の頭の中はこんな風に整理されてて、それが俺にもわかる、ってことなんじゃないかと思う。
「じゃあ、次はあなたの番ね」
そう言って、ライヒおばちゃんはこちらへ向き直った。
そして言った。
おばさんのイマージュの中、その世界では、何かの病気の治療として、あるいは治療とは関係なく、とにかく誰かが「手洗い」しているらしい。
かきまぜ器がボウルにあたる音がしつこく、それを使っているおばさんがいてしかし。
繰り広げられるのはかきまぜ器の回転にともなった鼻歌の伴奏(それは聴こえてきませんが)。
おばさんの想像の世界、聴いてる我々がおばさんの想像を聴くがしかし。
何かのゲーム、敵enemyがいる状況に接続され、それもかなりしつこく、ふざけたところも数分間。
洗濯板や日用品で演奏していたという音楽、ライヒおばさんがメレンゲづくりに箒の動きをレレと動かしたところ…治験ジャズとは一体…?
ラジオ、ジョアン・ミロ
ここ最近ウクライナのラジオをブライアン・イーノが紹介していたアプリで聴いてる。そしたらディスクがどうだとか、そんなことどうでもよくなりそうだけど。個々のことは。
ジョアン・ミロの画集が好きだったので渋谷でやっているBunkamuraの展覧会を観てきた。前回のフィンランドのデザイン展が思ったより楽しかったので足を運んでみたがミロの絵は後半の日本に来日した際に描いた「すもう」という小さな絵や炭を使ったというくらいで、そんなに関心せず、ふうんと早足に観終わってしまい、とても幸せな人なんだなと思った。ゴッホかミロか二択で好きな方になれるならミロになりたい。でもゴッホの方が描いてて面白かったのではないかと思う。画家として生きて、その個人の人生だけがこの世でミュージアムという空間で鑑賞され続けていくのはどういう状況なのかと。それは何か描いたり作ったりしてしまったからに他ならないけど。帰りにココアモドキの方のMILOと、ジョアン・ミロと日本のタヌキのツーショット写真をもらった。これはいい。観たかった絵は画集より自分の背丈より大きな絵でした。そして知らなかった色も実物では見えた。それぞれの人が生きた一人ずつのミュージアムのような、ときのなかでの部屋があるなら、そこに優劣はないと、思うのです。
ソニック・アドベンチャー2 バトル
ゲームキューブのメインメニューで安ジェネリック系アンビを数分再生し、速度や世界観がどうかしているゲームをプレイ。
一人プレイではできないモードがあってその2人プレイの中の対戦がかなり楽しいゲームなのでSonud testモードにして曲を聴く
City Escape1 第一ステージの曲。メロコア。メロコアって楽しい曲だったんだなあ、と思い出す。ふだん聴かないので。曲の切れ目がわからない編集でループし続けるのでDJ Herveyが魔改造したディスコエディットのようにさっきから延々同じ曲を聴いてる。十回はとっくに!次に行こう。
City Escape2 ゲームキューブのソフトです。爆走。ギターがメタル、アニメタルベビ。
wild canyon ヒップホップ。打ち込みのサックスぽいのがおもちゃの笛のようで良い。ジャック・デラ・ロッチャばりにキレがある。
Green forest 関西出汁とドドンパ娘。
気分を変えてゲームプレイ
チャオガーデン 池のデジタルホワイトノイズ 猫の鳴き声 赤子?redchild 溺れそうな ア・プ・プレ? あうあう
チャオカラテ チャオなるキャラが闘うのだが、やる気がなくなったらB連打がにぎかやし応援してチャオのやる気を出させる。他力というか。他力大事。他力本願て言葉はよくない、自力なんて一人の力、他力は一人以上。
このゲームの島から先は海に入れない、暗い海が不安にさせる見えない壁。
おでかけマシーン メニュー エスニック料理3分番組かわいいチープシンセが
ちからだめし 右から左にパンが振られてもどるタンバリンを模した音 延々聴いてるメニュー画面。
最初の部屋にもどる ハードなテクノ、音量上げる! 手癖で弾いてそうなメロ。
年間ベスト バッファローマッキー編
年間ベスト 2021
バッファローマッキー編
書き疲れました…修正したいところがあるけど、もうこれで。
音楽
今年リリース
1.Assadinhos – Winkadinka
ブラジルの40% Foda/Maneiríssimoから様々な変名を使ってリリースするGabriel Guerraという人物がフュージョンに影響を受けて作った楽曲で一曲目のsmoke on the waterをもじった(旋律もひねった)Smoke with the waterから最後まで飽きさせない。
こちらもGabriel Guerraの変名によるレーベル初期(2013年)のリリース。この頃は使用機材がリストアップされていて、音を作るのが好きな人はそれらを見るだけでも楽しめるかも。
☆ちなみに見やすいように番号を振っていますが、自分自身も音を作る側の人間なので人の作品に優劣の順位を付けることはしません。だってその時々で聴きたいものなんて変わるし。
(どれがナンバーワンだとか、そんなことしたら「”お笑い”っていうツール」でバトルしてるのと同じようなもんじゃあないですか)
2.DJ Harvey/VA – Mercury Rising (Volumen Tres)
2曲の想像のバックストリートボーイズみたいだけど絶対違う人たちの曲のダサ感にえっっと戸惑いつつ聴き進めて行くと、完璧なタイミングで(購入すると全曲聴ける)6曲目Mozaika – Never See You Againが◎鏡の部屋のVIPルームで真昼間から繰り広げられる仮面乱交パーティー。あるいはコスミック出版のインモラルDVDセットに入ってるどうしようもないB級映画でかかっていたらサイコーな曲。
Mozaika
一曲目のパフィーかラジオスターの悲劇かって曲ではなくCrepusculeという曲も◎
こういうのを聴くと、イビサに遊びに行ってみたくなる。学生の頃はイビサ系のコンピを聴いて「ダっさ!!」と即ゴミ箱に入れていたが、このごろはなぜ自分はイビサに呼ばれるような音楽を作ってこなかったのだろうかと悔やんでいます…。
3.Ripatti – Fun is Not a Straight Line
Vladislav Delayがジューク/フットワークをやるときの名義っぽい。テクノとか聴いてる感覚で聴ける。4曲目speedmemoriesで「プリッ!?パイパイ!」「ウッウッ」って連呼してる(サンプルが鳴ってる)のがいいですね。
4.I AM THE CALLING OF ME
( HIEROGLYPHIC BEING 「 WHEN LOVE KNOWS NO BOUNDS」収録曲)
ダンスっていう行為は自己を解放すると同時に深いところにある自己を表に引っ張り出すことでもある。つまり、自分を無くそうとしながら自分を見つけていく。それが言い表されている素晴らしい曲名だと思いました。アルバムでこの曲だけ購入。
5.Loren Connors – Domain Of The Wind
一度耳にすると思い出して時々聴きたくなるのがローレン・コナーズだと思いますが、この作品では「それやっていいの?」と思う箇所も繰り返し聴いていくと面白く、アンビエントやニューエイジ風味を足しても、そもそもの演奏が親和性があったのか昔の演奏より良くなっていってるところが、ローレン・コナーズを聴くと別のローレン・コナーズの作品を聴きたくなる不思議さがあるなあと。(映画館で映画を観ると帰宅してもう一本観たくなるのと同じように。)
6.HATTORI Takashi – NOISE
祝?完成!タカシマンの作曲について質問させてもらったので、それは近々タカシマンのnoteに記載されると思うので、そこで読んでもらえたら。
7.Alexandra Spence & MP Hopkins – The Divine For Me Is Whatever Is Real
詳細不明。ギリシャのレーベルから。バナナが浮いてるジャケ、これに似たフライヤーを以前作ったので親近感から。こういうのを一概に物音系っていうのは安易。脳死に等しい。内容が良いか悪いかっていうと良くも悪くもない。でもこういう音楽って良いとか悪いとか言えない音なので。ベストリリースっていう言葉ではすくい切れない。もしかすると人によっては良い悪いはあるかもしれませんが、ただ何かが鳴って消えて、それが何かわからなかったし記憶に残らなかったとしてもいいんじゃない?無意識の時間を意識の時間にしなくてもいいと思う。
☆これまで年間ベスト選出イベントに否定的な考えでしたが、この「千のミル」で今年は年間ベストを発表しようという話になったので、ここに記してみました。
8.Merzbow – Mukomodulator
SUPER PANGは全然追えてないけど。買ったけどどれを聴いたか覚えてないいメルツボックスはそろそろ全部聴かなきゃなぁ。
- Vindfængsel – You Can’t Regret What You Don’t Remember
ロシアのナズローから出たリバーヴがめちゃかかったピアノ作品。「覚えていないことは後悔できない」というタイトルも良い。どんな人かオーナーに聴いたが直接会ったことはないのでよく知らないんだとのこと。
ナズローレコーズからはBUFFALOMCKEEのカセットをリリースしたり映像を撮って送ってもらったりとこの一年とてもお世話になりました。
10.Spor Tranquil – Traces
この作品は私がSpor Tranquilに映像を撮影して送ってほしいと頼んだのが発端となり出来たアルバムのよう。ファンキーっていうのか… https://www.youtube.com/embed/TifSYBq-Gmw
今年JOYBEAMという映像の特番?を始めてみて、思ったより回数を重ねれてないけれど、来年も続けます。
来年一回目はBen Sanair特集。
11.LOST FROG PRODUCTIONSのリリース群
https://www.lostfrog.net/
レーベル特集ということでJOYBEAMでTwitchを使って10時間以上にわたってこれまでにロスト・フロッグ・プロダクションズがリリースしてきた、幅広いと一言で言い表すには多様過ぎる音楽をかけさせていただきました。しかもオーナーの解説付きで、素晴らしい時間だったなぁと。
そのLOST FROG PRODUCTIONSからリリースさせてもらったKINGDOM SCUMとのスプリットは、自分が作った方はさておき、キングダム・スカムの音源はとても素晴らしいと思います。ジャケも最高。
https://archive.org/details/lf131mp3
旧譜も混ぜて書こうとしたが力尽き断念。
映画
1.DAU ナターシャ
凄い数のエキストラを使った実験!とのことで見に行ってみると登場人物が数人しか出てこない序章だった…せっかく観たのに続編は観ず。日本語字幕なしならネットで観れるらしい。
2.クー!キンザザ
リメイクというのは前作との差異ばっかり気になってしまう。こっちはそれほどでもなかった。
実写のほうはあらためて見直して、二章に入る際に用語解説が挟まれる構成等、傑作だなとより一層楽しめた。特に皆が恐れている権力者はプールで遊んでる気弱なあほでしかない描写とか、物語後半に寄る星の住人とか。
3.聖なる犯罪者
犯罪者も改心して聖職者になってもいいんじゃない。日本では坊さんは…と言われてますが。
4.ブラックウィドウ
あんまり、こういうの観ないんで、サクッと駄菓子を食べるノリで鑑賞。
妹のミッドサマーの主演の人も良かったですね。
5.ワイルドスピード・ジェットブレイク
車が宇宙に行くバカ映画です。ツッコミどころしかない。
他のワイスピは一本も観たことありません。
まったく何も考えてなさそうな映画で人生の時間をくり抜かれるのが嫌な人もいるかもしれないし、自分も観るならそこから何か得たいと思っていたほうだけど、こういう頭を空にするのもいいと思います。
6.モンスターハンター
バイオハザードの夫妻の新作。バイオハザードの4か5あたりは兵庫のイオンシネマで観た。ファンタスティックフォーとか、辛い鑑賞記憶。
ゲームのモンハン・ライズは途中で止めてしまってます。
7.ザ・スーサイド・スクワッド
ワイスピ・ジェットブレイクに主人公の弟役として出てくる俳優がニヤニヤさせる妙な面白さがあるなと思っていたら、続けて観たこの映画でブリーフみたいなの履いていて、この人自分のこと良くわかってるなーと感心。やっぱり最後のボス戦でアメコミ映画のバトルシーン絵になるところで自分はややダレてしまったが、振り切った笑いを提供してくれる映画が好きなのでした。そして常々、お笑いだけをやっている人はこういう映画に負けてると思っていますがどうですか。
8.死霊館 悪魔のせいなら、無罪
死霊館シリーズも一本も観たことない。今までは前作観たことがないから観て予習してから行ったりしたが、そういうのはどうでもよくなった。
エンドクレジットの悪魔の声が録音されたテープが一番こわい。
ほんとに何も考えてなさそうで、あまりに何も考えてないがゆえに頭を空にされるというわけでもない類の映画。
9.DUNE
リンチの方を少し前にもう一度観て、キツイとこはあるけど観れなくはないかな?と思い直して、新作のDUNEを。
劇場は満席で、なかなかそんなこと久しぶりだったし、IMAXで鑑賞したのに(?)映写機の前にハエが止まって赤青黄色に分解されたハエのシルエットが時々映るという、今後なかなかなさそうな映画体験だった…終わって外に出たらお客さんは映画館スタッフに文句言ってた。
映画自体は…こういうもったいぶった批評文とか書く人いるよね、ていう。そういうのをデューン系って呼ぶ。
10.最後の決闘裁判
話の内容とは別で演じた俳優のマット・デイモンがあまりに良すぎる。ベン・アフレックに向かって天と地のなんとかに賭けてうんたら、と叫ぶとことかめっちゃ良くないですか。マット・デイモンは「リプリー」とか「インターステラー」とかキモい役を演じた時が真骨頂だと思ってる。
11.グリード ファストファッション帝国の真実
名画座で。マイケル・ウィンターボトムは「バタフライキス」が面白かったけど内容覚えてない。10年くらい経つとほんとに忘れるし覚えていると思っていてもその覚えている結末と見直した結末が違う。違う時間の世界に飛んでしまったような気分がします。「24アワー・パーティー・ピープル」はすごいつまんなかったけど見直そうと思ってる。
12.ビーチ・バム まじめに不真面目
「グリード ファストファッション帝国の真実」と一緒に。今年レンタルして観た「スプリングブレイカーズ」と同じ感覚もあって、どっちも登場人物たちがトリップしているときに話している馬鹿話でしかなく途中からは実際には起こっていない事としても観れる。
この映画をどっかのおじさん達が青春思い出話と絡めて話してたのを聴いたし、若い子はハーモニー・コリンは途中でおしゃれになったとか言ってたけどそんな映画じゃないと思った。日本で映画をちゃんと紹介できる人材不足、危機感を感じた…
13.ディア・エヴァン・ハンセン
まったく下調べもせず行って、劇場入口に貼ってある全米が泣いたミュージカルの映画化と書いてあるのを観て声を出し、間違えた!と思いながら席へ。上映開始すぐ、これが今から一時間以上続くのか…という驚き、後悔。
笑ってはいけない話のはずなのに主役の顔が喜劇の方が似合うし、ミュージカルといっても画面に出ている全員が踊りだすことはなく、しんみり独り歌うだけ。それがこの映画のテーマなのはわかっているけど、やっぱり面白くない。これでほんとに自殺止めれると思ってんのかな…。ただ途中の、ネットに上げられた動画がバズって、その動画に勇気づけられた人たちの顔が集まって一人の大きな顔になるドラゴンボールの元気玉が放たれるところは笑ってしまった。
14.マトリックス・レザレクションズ
いろいろ語りたくなる映画だと思う。アナリストが一見高速で動いてるように見えるシーンは、マトリックスという映画はバレットタイムになるとスロー再生になるのでそれを逆手に取ったっていうギャグなんですか?
新宿TOHOのTHX+ドルビーで観たせいか、他の映画を同じTHXで観てないのでわからないけど、音がすごく気になった。友達と話したら音全然聴いてなくてびっくりしたけど、他で観たらそんなに気にならないのかな。
劇中でロックをかけまくると「ネトウヨとかが喜びそうなカッコイイ」映画になってしまうことを回避して今回のオーケストラ中心の音楽なのかもしれないと想像したけど、それにしてもいまいちだったんで。マトリックス以外でも映画の画面消して音だけ聴いてると無駄にクラシックや音楽がずっとなっている映画はけっこうあるけど、それが見疲れたりする原因、面白さを奪う原因になってると思う。音作ってる人はもっと映画の音も聴いてると思うし、映画評論家は音に触れてなさすぎでは。
最後にかかる曲(レイジのカヴァーだと聞いた)も、原曲に比べたらよくないし…。マトリックスの世界で目覚めたとかどうこう言ってもアイオっていう現実はあるわけだし、ねぇ…?
ネオ右翼に吸収されたトリロジーを回収する云々という話は、それはマトリックス以外の映画やどんな作品にも起こることだし、自分がそういう事をネットを観て予備知識として知って考えてみて、それについての答えは出てこないし難しい問題だと思っているが、自分はそれを人から語られることでしらけてしまう。
ネコちゃん猫ちゃん言ってる人はどう思ったんでしょう。
ラストとか全体的に、「神様メール」の方がすごいと思ったんで、観てください。
登場人物では昔からトリニティ派で、セキグチ・サトルとyuki kanekoとトニリティーというユニットを組んでいるし、このブログのアドレスもトリニティなので、そこはよし!って感じですよ。
15.ラストナイト・イン・ソーホー
MeToo運動で言われている腐った芸能界の話をストレートに。
加害者の男性はほとんど有象無象として描かれ、被害者の女性には顔がある。
ちょっとくどいくらいの描写や丁寧すぎる犯人明かしなど、間違って受け取られないよう揺らぎがない語り方で、スウィンギンロンドンとか呼ばれてた時代の裏側というかもはや表はこんな酷かったんですよと。
劇中流れる楽曲のなかでもcilla blackの「you’re my world」で使われているストリングスが痛々しくて、ホラー映画で使われている恐怖の描写で多様されている音と同じ。この曲の使い方驚いた。
あとラストでビンタするときにパンが右から左に触れるのがオモロい。
どうしても長くなるお爺ちゃんの話のような「最後の決闘裁判」より、メタメタなマトリックスより(トリニティ救出前に現れる一作目で女の子だったという人物が出てくるあたりからすっごいつまらなくなって、そこからどうでもよくなってしまい)。
映画も旧作まで書くエネルギーなし。
ベストコーヒー
1.近所の珈琲
最高。教えないけど。
2.マウント・ハーゲン
カフェインレス、インスタント。がぶ飲み。
アニメ
1.Zガンダム
お兄ちゃんプレイに泣いた私は現在鑑賞中の「ガンダムZZ」で正規お兄ちゃんプレイを受けてます。
ゼータはほんとに観た人の心を破壊した作品なんだろうな…ズタズタに…。
以上、良いお年を!!
Cumbias Psicodelicas: Vol. 1 Ayahuasca (70’s Peru Cumbia Psych / Funk / Latin Soul) KILLER MASTERPIECE !!!
どうも909や808といったドラムマシンの音が聴きたいサイクルからチャカポコいうパーカッション・サウンドに好みが変わった。Yesの”Owner of a lonly heart”のイントロ、ペルーのV.A.、ラリー・レヴァンのミックス。
https://repsych.bandcamp.com/album/cumbias-psicodelicas-vol-1-ayahuasca-70s-peru-cumbia-psych-funk-latin-soul-killer-masterpiece
コージー・ファニ・トゥッティ『アート・セックス・ミュージック』

前々から読みたかった本を。
最初にThrobing Gristleのことを知ったのはスタジオボイス2004年6月のザ・ニュー・ノーウェイヴ特集号でだった気がする。そのときは未聴ながら読んだ記事にはグループ名をスログリと略す人がいるだとか書いてあったことだけ面白くて覚えており、それからすぐにベストとリミックスを友人から借りて聴いた。あのリミックス良かったな。聴きたいが手元にないけど。
その号には別のページにWOODMANとMOODMANが写真付きで掲載されており、名義を使い分けている同一人物なのかと、ウッドマンが片腕をあげてタワシか何かを片腕で腋に押し当てている写真の意図不明さも相まって理解が追い付かず、おまけにMOODYMANNもいるということでいろいろ気になる号だった。しかしその時の友人に貸したら回し読みでボロボロになって路上に捨てられたエロ本みたいにズブ濡れになって返ってきたので処分した。
その後TGのオリジナルアルバムを彼らの伝説と合わせて楽しみ、デレク・ジャーマンの映画で物足りなさを感じ、映画『デコーダー』のジェネPを観て号泣した。こんな奴がいるのかと思って。
クリス&コージーはあまり聴いてない、そんな状態でこの本を読み始め、つまりほとんど何も知らない状態でこれを読んでみたら60年代のヒッピームーブメントどっぷりでヘルズ・エンジェルは出てくるし、セックス・ピストルズの名前まで出てくることにとても驚きながら読み終えることができた。例えばほぼなかったノイバウテンの話なんかはもう少し出てくることも少し期待したけれど。
生まれてから始まる他人の自伝なんてあまり読んだこともないし、早くTGの頃の話が読みたくって飛ばしそうになりながら読み進めていくと意外にも早い時点で物語りに惹かれ楽しむことができた。TGで一番好きな曲は「Distant Dream (Part 2)」なのだけれど、少しだけ触れられていたことにも満足。ネットで調べても出てこないけれど、パート2ということはパート1があるのか(ボーカルなしバージョン?)、使用した機材の詳細等まで書かれていたら最高だったけど…。この曲が描く魔法陣というか怪しい雰囲気とアシッドなシンセ、チャカポコいってるだけのリズムボックス、機械的なメロディ、どれも大好きだけれど特にシンセは何を使ったのか知りたい。
https://hivmusic1.bandcamp.com/track/gen-defekt-distant-dreams-part-2-throbbing-gristle
ジェネPが亡くなって追悼で出ているアルバムのこれは原曲に近いカヴァーで好感がもてた。動くジェネPを初めて見たのは『モジュレーション』というミュージシャンがどうやって音を作ってるか話してくれたりするDVDで、いきなりRolly(ローリー寺西)に似た人が画面に表れて、それを見せてくれた友人と爆笑したことを覚えている。その当時なかなか手に入りにくい貴重な内容のDVDだったけれど、今ではあれに等しい内容かそれ以上のはいくらでもネットで観れそうですね。
結局Distant Dream(Part2)の路線を引き継いだとはいえあれと同じ感覚のテクノでもないパーソナルスペース内で弧を描くようにブレインダンスする曲はTG後にそれぞれが始めたユニットでも無いような気がする(もしあるなら教えてほしいです!)。TGファミリー以外のものでもあの曲と同じ感覚で編纂されるコンピレーションがあるとすればそれも聴いてみたい。リズムボックスとベタ打ちみたいなメロディ・ベースにアシッドハウスではないアシッドなシンセの組み合わせ。(これを読んでくれた方、それぞれ作ってみて下さい。※聴かせて。)
ジェネPほんとひどすぎだし、面白いんだけど、特にいいなと思ったのは下記に引用を。
P79
ファンハウスは平和に静まり返っていた。わたし、ジェン、そして2、3人を除き、住人のほぼ全員がワイト島フェスティヴァルに出かけた後だった。自分たちだけで建物を独り占めできる状況を楽しんでいたところ突如として強烈なオートバイの咆哮が耳に入ってきて、ヘルズ・エンジェルズの連中が表のドアを押し破ってハウス内をバイクで乗り回し、壁にスブレーで落書きし略奪行為に及ぶものすごい騒音がそれに続いた。どうしたわけか、彼らは建物の最上階にまではやってこなかった。騒音がおさまったところで彼らも落ち着いたのだろうと察しをつけ、わたしたちがこっそり静かに階下へと降りて行ったところ、そこで出くわしたのはエンジェルズの面々が居間に集合して「メンバー候補生」のひとりを取り囲み、その口をエイジャックス社製のトイレ用粉末洗剤でごしごし洗っている光景だった。
P86
ジェンの関心の中心にあったのは音楽だった―ーそれでわたしも彼に出会うことになったのだ―ーし、彼とスパイディーとその友人連中は音楽で実験してきた。ただしその音楽はザ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンド、ザ・ファッグス、フランク・ザッパといったもっと分かりやすいアングラ・バンドばかりではなくスパイディーの一風変わったレコード・コレクションのいくつかからも影響を受けていて、中でもとりわけAMMの霊感に満ちたあまり知られていない1967年のアルバム『AMMMusic』はスパイディーが奥奮しながら絶対ジェンに聴かせると力説した1枚だった(*21)。AMM1コーネリアス・カーデュー、キース・ロウ、ローレンス・シーフ、ルー・ゲア、エディ・プレヴォストらの音楽に対する哲学的なアプローチは大きな影響を及ぼすことになったし、それはまた音楽に対するCOUMのアプローチなっていくもののはしりのヴァージョンのように思える――和声の排斥、所定の楽器を演奏する能力は誰にとっても必須条件ではない、「グループ」の生み出したサウンドもまたグループ自体にとっての寄与メンバーと看做す、といった具合だ。
P111
モッズ、フィッシャー・キッズ、スキンヘッズ、ヘルズ・エンジェルズらは互いに争い合った―ーこれらのグループはすべて、平和を愛するヒッピーめいた面をちょっとでもにおわせる人間なら誰でもお構いなしに敵対心を示し攻撃を仕掛けてきた⋯⋯わたしたちもここに一括されていた。なるほど、わたしたちの装いは確かに目立っていたし、特にジェンが蛍光オレンジ色の服を着たときはそうだった。けれども好きな格好をする権利が自分たちにはあると思っていたし、それに対意に満ちた注視が向けられることは予想の範勝でわたしたちも容認していた。
P115
カンタベリーで過ごした時間は素晴らしかった。ジェンは『死んだ通行人(Dead Pedestrians)』をフィルム撮影している際に車道で倒れたふりをしたため「横断歩道を不当使用した」かどであわや逮捕されそうになったし、レズ(レヴ〈=聖職者〉・モウルとして)は牧師の衣装ですっかりなりきってカンタベリー大聖堂の前でポーズをとった。わたしたちはあのギグを『著作権侵害(CopyrightBreeches)』(だ完全形で演じたことはない)と称したが、それはデュシャンのレディメイド作品『自転車の車輪』に基づくアィディア、そしてまたジェンがフルクサスの面々と彼らの作品の権利をめぐって口論になった経験からもきていた。
P139
出発の前日にカルト教団「神の子供たち」のローカル支部から訪問を受けたが、彼らは以前からわたしたちの救済に取り組んでいた。この訪問は特に、わたしにはもはや望みはなく、地獄に堕ちる定めにあると伝えるためのものだった―ーああ、それからわたしたちがいなくなったら家を略奪する、とも。なんとも素敵な連中だった。母、祖母、パムがやって来て、少々悲しがっていたもののわたしのために喜んでくれていた彼女たちはお別れを告げ今後の幸運を祈ってくれた。フィジーはさよならを言いに家に顔を出さなかった―ーわたしたちが去るという事実は彼にはまだショックが大き過ぎたのだ。ハルでの最後の夜をわたしは孤独とよるべのない悲しさにひどく苛まれて過ごした。
P176-177
自分自身のイメージおよびアイデンティティの権利を放棄するというのはプロジェクトの重要な部分だったしああした様々なイメージを共同で生み出していく過程で得る経験と同じくらいわたしはそちらにも興味をそそられた。自分が「サンダーランド出身のテッサ」であろうが「ピカデリーから来たみだらなミリー」、はたまた「ジェラルディーン」、「スージー」、「コージ―」であろうが、わたしは他の女の子たちとまったく同じ、マスターベーションのための性的ファンタジーの材料だったのであれ(わたし自身の)現実に近過ぎるものはその幻想を霧散させてしまう。自発的な参加者としてわたしは自分自身をそういう風に利用されるポジションに位置づけたし、そうやって1970年代のフェミニズムからの攻撃の矢面に立つことになった。男性による女性の性的な搾取および擬物化はフェミニストたちにとっての熱いトピックで、彼女たちのアジェンダの中でもとても高い位置を占めていたし、そこでわたしやそれ以外のセックス業界で働く者たちは敵と看做された。わたしは1970年代のフェミニズムと自己同一化していなかった――あの思想は自分を代弁していなかったし、多様かつ複雑な女性の本質を代弁するものでもなかった。わたしは自由な精神を持つ人間だったし、自分自身のとった行動に関してまたさらに規則だの罪悪感だのを投げつけられるのは真っ平だった。ええ、セックス産業で仕事をすることで確かにわたしは彼女たちが闘っていた対象に貢献していたけれども、それは必ずしも自分が彼女たちの敵を是認していた、ということではない。わたしは搾取の「犠牲者」でも何でもなかった。自分自身の目的のためにわたしはセックス産業を搾取していたのだし、そうやって彼らをくつがえし利用することで自身のアートをクリエイトしようとしていた。あれはわたし自身の選択だった。セックス産業の内実を内側から知りたかったし、そうやって実体験者としての立場から語りたかった。自分の作品に純粋さを持たせたかったし、そうすることで既にあった周囲の抱く期待や自分自身の中にあった制約に反発し、またターゲットに設定されていた市場も含むセックス・ビジネスに関わっていた誰もに課せられた複雑なニュアンスや試練をすべて理解したかった。わたしはルールの限界を越えようとしていたーーそこにはフェミニストたちのルールも含まれていた。わたしは自分の人生を「個人」として生きているし、すべての選択肢はわたしにだってそれ以外の誰にだって等しく開かれたものだと思っている。
P221
クリスの専門的知識とTGに対する献身ぶりとは妥協なしでかけがえのないものだった。彼はジェンがその中に入れるくらい巨大なベース用スビーカー2基をスタジオに組み立てていた。高音用のツィーター・スピーカーと相まってあれらのおかげでわたしたちの周波域は広がったし、皆で一緒にプレイする際のサウンドに本質的なパワーを、そして楽しさとインスピレーションとをもたらしてくれた。TGのギアはかなりの高速に入っていた。けれどもクリスもわたしたちも、後になってライヴをやる際にいざあのベース・スピーカーを地下スタジオから引っばり出して狭い階段を使って運び上げ、ドリスに積み込まなければならなくなるまでそれがどれだけ大変かは考えてもいなかった。スピーカーを階段の手すりの上に持ち上げなければならず、がんばるスリージーの顔はほとんど紫色に近くなった⋯⋯
P243
自分たちはやっとどこかに向かいつつあるぞ⋯⋯と感じ始めたところでジェンはそれで充分と判断し、そこでおしまいにしてウィンビーに行きたいとか家に帰ってホット・チョコレートを飲みたいなどと言い出すのだ。あれに特にクリスは怒らされ苛立たされたものだったが、わたしも同様だったのは、ジェンが家に帰るなら当然わたしもついてくるものと彼が思い込んでいて、そうではなくわたしがスリージーとクリスと一緒にスタジオに残る方を選ぶなどとは思ってもいなかったからだった ― 一緒に帰り、わたしは彼にホット・チョコレートを作るものだ、と。あれでクリエイティヴィティの流れやサウンドの実験が中断させられたし、わたしたちの練習の中核は好きなだけ探究する自由だったにも関わらず、求めてもいない、不当な制限がスタジオで過ごす時間に課せられることにもなった。
P255
“ホット・オン・ザ・ヒールズ・オブ・ラヴ”のヴォーカルに(いくらか、という程度だが)似通ったところを感じさせるシングル『アドレナリン/ディスタント・ドリームス』の頃までには、自らのリード・ヴォーカルの領域が脅かされているとジェンが感じていたことをわたしたちも全員察知していた。”アドレナリン”に関してわたしたちの意見は食い違った――わたし、クリス、スリージーの3人はあれをインスト曲にしたがっていたが、ジェンはヴォーカルを入れたがり、他の誰かが歌で何かることにも、また妥協策としての共同ヴォーカル案にも耳を貸さなかった。彼の不平はあのトラックや”ディスタント・ドリームス”ではヴォーカル以外に彼の出番が何もなかったせいだったのかもしれない。あの2曲はTG解散後、わたしとクリスがクリス&コージーとして進んでいくことになる方向を示すものだった。
P263
恒例のわたしの誕生日祝いの1980年版はベック・ロードでの花火パーティで、新旧入り交じった友人たちにポーラも含む面々が集まった。幸せそうで普段より陽気なジェンの姿を見るのは嬉しかった。わたしはポーラが好きだったーーわたしたちはウマが合ったし今も友人付き合いは続いている。2日後、ベルリンの5Oクラブとフランクフルト会場での2公演のためTGはドイツにいた。カスタム・メイドの新しいコンパクトな運搬ケースで機材を運んでいたので、セットアップを素早くやれるようになっていたのはラッキーだった。というのもわたしたちのショウの前に割礼儀式がおこなわれ、その会場清掃・後片付けが終わるまで待たなければならなかったからだーたとえ自分としては断固反対で残酷な行為だと感じたとはいえ、TGギグの前に新生児のペニスが血を流すというのは何やらふさわしくもあった。あのギグの場でわたしたちはクリスの出す素晴らしくインダストリアルでメカニカルなリズムに触発されたTGの新曲をクリエイトした。ジェンがわたしたちに何につえばいい?と訊いてきた―「教練(Discipline)」とわたしとスリージーは答えた。もっともアイコニックなTG曲のひとつはこうして誕生した。
P314-316
アルバムをレコーディングし、ツアーてアルバムを「売る」ためにそれをライヴで演奏するとの発想は、わたしたちには目新しいものだった。というわけでサポート・バンドをツアーに帯同させるというのも目新しい体験だった⋯⋯SPKが相手だ。この時点で彼らの顔ぶれはグレアム、彼の妻シーナン、そして追加ヴォーカルおよびダンス担当のカリーナ・ヘイズの3人だった。彼らの機材の量は小道具の数々にアングル・グラインダーまで含むわたしたちのそれ以上のもので、空港で何度も足止めを食らいトラブルを起こすことになった。海外ツアーをおこなう際に「装置用カーネイ」(他国間で機材・備品を移動させる際の一時的な輸出/輸入書類)の申請は義務づけられていて、これは悪夢だった。税関通過の時点で機材のあらゆるアイテムはリストに記載されその所在の責任を負わなければならなかったー導線、端子ジャック、電源装置のひとつひとつにいたるまで。そのひとつでも行方不明になると、相当な額の罰金を課せられることだってあった。この面はただでさえ短かった空港間の乗り継ぎ時間に余計なストレスをつけ加えてくれたし、もっともそれすらグレアムの所持していた風変わりな荷物が生み出す数々のすったもんだ劇を除いて、の話だった。
背後に横たわる不服のタネを最初にグレアムの中に引き起こしたのは、わたしたちがアメリヵで入国審査を受けた際に、彼シーナン、カリーナが待ったをかけられ質疑応答のため別室に連れていかれたときだった。わたしとクリスが彼ら3人は正真正銘我々のサポート・アクトであり、その保証人になると提案するまで彼らは入国を許されなかった。この応対は功を奏したが、と同時に公の場でグレアムがわたしたちの部下に当たる存在であることがはっきりしたのを彼は良く受け止めなかったし、入国審査官がわたしとクリスに笑顔を見せ、「今夜のショウのチケットを持ってますーあなたたちの音楽が大好きなんで」と声をかけてきたとなればなおさらだった。わたしたちは彼にC&じのバッジをあげ、少しおしゃぺりし、その場を去った。わたしたちの従属アクトとして扱われているというグレアムの抱いた感覚は、わたしたちがショウでトリを務め、また現地で受けたラジオやマスコミ取材の本数が彼よりもわたしたちの方が遥かに多かったことで増していった。いわゆる「ヘッドライン」の座を占めるのは誰かという点はわたし自身には重要事ではなく、ほとんど意味は持たなかったが、グレアムにとっては意味が大きかった。事態は非常にぎこちないものになっていったし、ひっきりなしに文句を言いダンをうるさがらせるグレアムの存在はツアーに思いっきり水を差した。その矛先をダンはすべてもゃんと受け止めていたが、グレアムの気分をなだめようと彼が何をやっても無駄だった。観客の頭上で金属製チェーンを振り回す、会場からレンタルしたマイクをぶんぶん回して壊す、その場で見つけたものなら何でも手当たり次第、会場の支柱を含む様々な物体に研削機をかけることで散る火花の危険⋯⋯といったグレアムの振る舞いでSPKがパフォーマンスを通じて会場側に与えた損害に対する様々な苦情・金銭面での代償を何もかも処理することで、ダンはツアーを軌道に乗せ続けていた。あるショウを観にきた若い女の子のお客は重たいチェーンの激しい一撃で頭に裂傷を負い訴訟を起こすと脅しをかけてさたが、ダンはなんとか彼女を説得して起訴を免れた。
グレアムの抱える不平にさんざん悩まされ、状況はツアー半ばで限界に達した。またもや起きたグレアムとの対立の1幕を終えて通りを歩いていたところ、ダンが唐突に足を止め、「もうたくさんだ!俺は降りる!」と叫んでツアー用のブリーフケースを通りに放り投げた。ニックはその光景を怖がっていたし、ツアーがどうなってしまうか自分たちにも見当がつかなかった。わたしはブリーフケースを取り戻しにいき、誰か代役が見つかるまではツアーに同行して欲しいとクリスと一緒にダンをなんとか説き伏せることができた。彼はその後グレアムを避けることにし、ツアマネ業務を引き継ぎグレアムと平静な状態を保つべく助っ人に現れたスティーヴ(・モンゴメリー)と入れ替わったところで、わたしたちは彼に感無量の別れを告げた。西海岸に到着するや、わたしたちは早速ニックを友人たちに会わせることにした。ピリピリした雰囲気から逃げ出せたのはありがたかった。SPKが生み出した損害経費はツアーの進行に伴いかさんでいき、最終的にツアー収益のかなりの額を食いつぶすことになった。帰国便をつかまえるためにスティーヴが全員を空港に連れていってくれたところでギャラの清算がおこなわれることになっていた。ツアー収支の状況を伝えられてグレアムは怒り狂った。「俺には養わないといけない妻と子供がふたりいて、家のローンの支払いもあるんだぞ!」と彼はわめいた。クリスはその場をおさめ事情を説明し彼を納得させようとしたが、彼自身がスティーヴと交わした契約書の内容に反してグレアムは金を要求してきた。彼の求めるギャラはわたしとスティーヴの報酬を削って捻出するほかなかった。スティーヴは男性トイレに向かい、グレアムはその後についていった。両者がトイレから出てくると、スティーヴは見るからに動揺した様子で、一方グレアムはわたしたちに向かって一言も残さず走り去っていった。わたしはニックの隣に座り、周囲で何かしら良くないことが起きているのに気づかないように彼を守っていた。「どうしたの?」とスティーヴに尋ねた。「あいつに不意打ちを食らわされた。まさか口で罵るだけじゃなく実際に手をあげてくるとは思わなかった」この口論の様子を目撃した男性がいたらしく彼はロサンジェルス警察に通報していて、現場にやってきた警官はスティーヴに対し、ツアー・マネージャーとしての彼にはグレアムの身の安全とオーストラリア帰国とを確保する責任があるとし、スティーヴはグレアムに報酬を支払うべきで、さもなくばわたしたち全員を分署に連行すると申し渡した。スティーヴは彼が受け取るはずの歩合金を失い、わたしたちは自分たち自身のツアーの成果として数100ドルしか手元に残らなかった。ぼったくられた思いだった。SPKはあの後に解散したと耳にしたし、その後グレアムはLAに移住してハリウッド映画向けの音楽をやるようになった。
———————————–
———–
https://hieroglyphicbeingofficial.bandcamp.com/track/i-am-the-calling-of-me
Hieroglyphic beingの曲「I am calling of me」、なんちゅうかっこいいタイトルや!と購入。リメイクでない方の「トータル・リコール」を幼心に直撃している者として。このコージーの本にもそれを感じた。

5 букв радио – sultan seth, psee, dolphin hospital @ high castle 26aug2021
electronica ほとんど手元に残っていないこのジャンルの曲を聴きつつ、猫も杓子も皆夢中だったエレクトロニカと呼ばれた音楽で残暑を室内クーラーで殺して松と雅の侘び寂びってか……
あの頃(体感約18年前)最高のエレクトロニカを我は創らん!と息巻いていた皆は一体どこで何をしているの。地球に優しい暮らし、とかなのかなあ……?
そして前振りとなんの関係もなく、ロシアNazlo Recordsが教えてくれたビデオをいま観ております。
彼らのスタジオでのライブ。
あのロシアのメーカーのシンセドラム使ったりしている。
5 букв радио – sultan seth, psee, dolphin hospital @ high castle 26aug2021
✎ナズローからはカセットテープがもう一本出る予定。夏休みしているJOYBEAMでも二回目の彼らの特集を準備中!

デイヴィッド・グラブス – 『レコードは風景をだいなしにする ジョン・ケージと録音物たち』
ちょうどさっき、沈黙を聴くのではなく『ワイルドスピード ジェット・ブレイク』を観てきたところ。このシリーズ9作目らしいけど今まで一作も見たことなかったよ。カーレース映画かと思ってたらそれは間違ってなかったけど世界を救う大きい話だった。
それに引き換え『爆走5000キロ』オリジナルタイトルはGUMBALL RALLY。くだらない日常に飽き飽きしたら「ガンボール!」の掛け声でいつでも発車できる。とてつもないエネルギー体とかが美術班がこんな感じかなって作ったシュルレアリスムとダサイバーが行きついた先のよなオブジェの中に入っててそれを奪い合うとか、爆音と破壊と車の演舞にCGは目を楽しませはするけど、フルオーケストラが鳴りっぱなしの映画鑑賞中から頭痛がおきた。音楽は進化しているわけではないが人は退化しているかもしれない。しかしスタントはすごい。
ダヴィンチ…ピカソ…スピルバーグ…黒澤明…世界で名を馳せる全ての人々は読んでいるとされるジョン・ケージの『小鳥たちのために』だとか、マイケル・ナイマン『実験音楽―ケージとその後』やデレク・ベイリー『インプロヴィゼーション』を読んだものの、雑誌や友人たちから伝説の~とカッコつきで語られていた印象のみが記憶にあって何が書かれていたか忘れるどころか覚えてもいない者として、後半はデジタルアーカイブについて考察しているものの、この本はもっと早く出ているべきだったと感じた。
昨年はこの現代において「さあみんなで4分33秒の沈黙を聴いてみましょう」と金を取ってやっている教室があるとラジオで聴いて絶句した。それなら詩でも散文でもない水蒸気のほうがマシではないか?
この本で面白かったところはケージへの批判がしっかり書かれていること。告白するがいままでケージの音源でこれは面白いなと感じたものはほぼない。まあそもそも枚数がめっちゃあるだろうしもちろん全部聴いてないけど。ただ「ヴァリエーションズ」のIVかVIIか忘れたけどケージ本人がやってるDVDは音がノイズだったのもあって面白く観た。あとは最初にプリペアドピアノの音色を聴いたときと、単調なピアノの曲で好きなのが一曲あったけどWinterだったか何だったか…チュードアがバシバシ鍵盤を演奏してる音の強弱が激しい音源も修行みたいに繰り返しかけたけど好きにならなかった。あとラ・モンテについて疑問を感じてる、明らかにトニー・コンラッドの肩持ってるふうな箇所とか。UBUWEBがトニー・コンラッドの映像と音が一緒じゃないと意味ないのに『フリッカー』の映像だけ無音で上げてたとかも書いてて…それ観たわ!となった。
正直この本が出たのは知ってたけど、グラブスのソロを聴いてライブも観に行ったけれども音楽はあまり好きになれなかったので、自分にとっては特にガスター・デル・ソルの2ndという名盤を愛聴していたもののタイトルもジョン・ケージって入ってるしレコードは風景を台無しになんかしねーよと思ったので、まさか中身がそんな単純な話ではないとも考えつつ読む気がしなかったのだった。
この本自体は全体として想定されているであろう内容の序章なのかなと思う分量ではあったのだが、一つ驚いた箇所は、晩年のピエール・シェフェールがその生涯に渡り取り組んできたミュージックコンクレートが失敗だと思っていたこと。
彼は人生を棒に振ったと、「ドレミの外では何もできない」と結論づけ、さらにはこれから録音された音を使って作曲をする人たちに何か伝えたいことはないかという問に対し、「音の世界を探求することは楽しいだろうが音楽をつくっているという思い違いをすべきではない」と答えたということに驚いた。まあ私はシェフェールについても有名なアルバムを聴いたことはあるにはあるにせよ何の感銘も受けなかった者ですが…人生、棒、おそろしい単語の組み合わせではないか。
そして喧嘩別れしたと伝えられているオルークの言葉の引用があり、肯定的に書いていることにも少々驚いた。少々下世話な話。
何かの本でケージが「自分の人生に対して、これでいいんだと言うこと」といっていた。アンビエントは心地よい音色の質感ではなく(だいたい提唱者が聴くことも無視することもできる音楽だと…)、インダストリアルはメタルパーカッションではなく工場勤務であり、身体性とは秒で脱いで上半身を披露するサービスではないならば、自分の人生のあらゆるすべてに対する赦しとは「今の自分が一番好き」だとか「もしも生まれ変わってもまた私に生まれたい」という揺るぎのないアイデンティティへの回帰や統合ではなく、自己を取り巻く環境が日々混沌に混沌を足して大喜利する状況へ向かうことをやめないことを思い出し、その都度これでいいんだと言えるならば…….

Vindfængsel – 『You Can’t Regret What You Don’t Remember』
「考えたくないから」
ラーメンサブスク
「覚えていないことは後悔できない」
https://nazlorecords.bandcamp.com/album/you-cant-regret-what-you-dont-remember